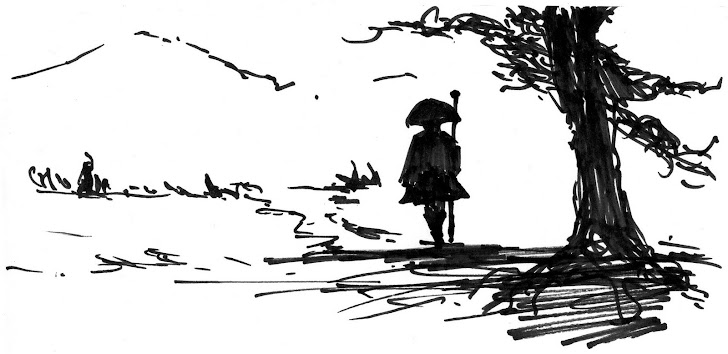この音樂を聞きながら作品を鑑賞して下さい。
これは自作(オリジナル)の
『YAMAHA QY100 Motion1(竪琴・harp)曲 高秋 美樹彦』
といふ曲で、YAMAHAの「QY100」で作りました。
映像は奈良懸にある、
『石舞臺』
へ出かけた時のものです。
雰圍氣を味はつて戴ければ幸ひです.
ない方が良いといふ讀者はご自由にどうぞ。
近江不忍(あふみのしのばず・Ohominosinobazu)
去年(2015)の初夏だつたかに、空樂音(カラオケ)喫茶『トミイ(TOMY)』から撮影を依頼されて、それ以降、度々撮影に出かける事となつたのだが、そこで店主(マスタア)の富田修氏が偶然にも俳句を嗜(たしな)んでゐるといふ事が、何氣ない會話(くわいわ)から知り得る事となり、實(じつ)は懇意にしてゐる三人の女性が合同俳句集を出版したので、是非とも讀んで貰ひたいと本を手渡された。
それが件(くだん)の『合同句集「三光鳥」』である。
生憎(あいにく)、筆者は三册の短歌集を出版しはしたが、句集には手を出してゐなかつた。
勿論、出版出來る句集は幾つか完成して手元にはあつたが、出版物として發表(はつぺう)するよりも、昨今は專(もつぱ)ら世界通信網(インタアネツト・Internet)へ書込(かきこ)む事で用は足りてゐるやうに感じてゐ、更に、筆者は俳諧の連歌における發句は詠むが俳句をする氣は寸毫もなく、これまでの發句の基本である「五七五・季語・切字」についても、少なからず意見を持合せてもゐるし、研究の成果をSNSで公開もしてゐる上に、「寫生(しやせい)の句」にも異を唱へてゐるで、俳句に對しての感想を述べるのに相應(ふさは)しいか自信はなかつたから、それを躊躇(ちうちよ)してゐたのである。
筆者の立場はこれぐらゐにして、本題の『合同句集「三光鳥」』の方に戻れば、さうであるにも拘はらず、その際ここに發表された作品の感想を述べるといふ約束を果たさなければならないのだが、さりとて一句づつを全て細々(こまごま)と語る譯にも行かないので、良くも惡くも筆者が氣になつた句に就いて意見を述べて見ようと思ふ。
一人目の作者。
まづ最初に、北村恭久子さんの句。
早春の絵本ひらけば水の音
これは本書の十五頁にある句で、筆者は『發句拍子論(ほつくリズム・A Hokku poetry rhythm theory)』といふ著書の中で「五七五」は『拍子(リズム・rhythm)』であると説いてゐて、それを示せば、
さうしゆんの ゑほんひらけば みづのおと
C♪♪ ♪ ♪†ζ┃γ♪♪♪♪♪♪♪┃♪♪♪♪†ζ┃
といふ俳譜で説明出來るものと考へてゐ、殘念な事に「註」として「八分休符(γ)・四分音符(†)・四分休符(ζ)」を代用して扱つてゐる。
一句は、早春の雪解け水の音が開いた絵本から溢れ出て來たといふ春と出逢へた驚きが傳はつて來る。
恐らく子供か孫にでも讀み聞かせやうとしたのだらうか、その優しさが奇蹟との遭遇を可能ならしめたのではなからうか。
新鮮な喜びに滿ちた早春の句と思はれる。
因みに、俳譜の上の假名(かな)表記は、筆者の獨斷で歴史的假名遣(れきしてきかなづかひ)とした。
目薬のうすももいろの四温かな
めぐすりの うすももいろの しをんかな
C♪♪♪♪†ζ┃♪♪♪♪♪♪†┃♪♪♪♪†ζ┃
この句は十六頁にあり、「四温」とは冬の大陸性気候の特徴で、嚴寒の頃に寒さが三日間續いた後に、四日間やや寒さが緩む現象の事である。
用例としては、
「三寒四温・三寒・四温・四温日和」
とあり、季語としては冬で、
「春への季節が一進一退といふ意味ではない」
といふ柱脚(きやくちゆう)があるが、寒さの後に温かさを感じながら、どうして春への思ひを浮べずにゐられようか。
「目薬の」容器か中の液體(えきたい)が「うすももいろ」であつたのを見て、その「ピンク(pink)」から聯想(れんさう)される梅や桃や櫻の花瓣(はなびら)の鮮やかな色を目に注(さ)す事で、この後にまだまだ寒さが續く事を理解しながらも、「うすももいろ」を腦裡(なうり)に直接映し込みながら、まだ來ぬ春を感じようとしてしまはないだらうか。
そんな風にこの句を讀んで仕舞はずにゐられない。
誰かいるような朧夜の行き止まり
たれかゐる やうな
おぼろ よの ゆきどまり
C♪♪♪♪†ζ┃γ♪♪♪ ♪♪♪ ♪♪┃♪♪♪♪†ζ┃
十九頁にある句であるが、中句が八音の字餘りであり、しかも始まりが「ような」といふ三音であるから「八分休符(γ)」を必要とする爲、「おぼろ」を「三連符(♪♪♪=†(四分音符の代用))で對應(たいおう)する外はなく、かくてかういふ鹽梅(あんばい)となつて仕舞つた。
ただ、この句は、
朧夜の誰かいるような行き止まり
おぼろよの たれかゐる
やうな ゆきどまり
C♪♪♪♪†ζ┃γ♪♪♪♪♪ ♪♪♪┃♪♪♪♪†ζ┃
といふやうに語順を變(か)へる事も可能で、この場合も中句は字餘りの八音であるが、三連符になるのは「ような」といふ最後の三音の言葉となる。
けれども、ここは「誰かいるような」といふ期待と不安の入雜(いりま)じつたやうな氣持を抱きながら、「朧夜」をさまよふやうに道を歩いて、不圖(ふと)路地の奧へと導かれたら、そこは「行き止まり」であつた、といふ意外性に滿ちた表現の初案に止めを刺す。
待ち伏せのような夜桜屋敷かな
まちぶせの やうなよざくら やしきかな
C♪♪♪♪†ζ┃γ♪♪♪♪♪♪♪┃♪♪♪♪†ζ┃
二十一頁の句であるが、先程の「行き止まり」といふ句と境地は似てゐて、「待ち伏せ」といふ驚きを最初に述べ、その理由が狂うような繚亂(れうらん)とした「夜桜」の所爲(せゐ)であると原因と結果を提示して見せたのである。
切字とは發句で『一句二章』を完結させる爲のもので、「かな」が將(まさ)にそれを物語つてゐて、上五句や中句に多く用ゐられる「や」と違ひ、「けり」などと同じやうに下五句にある切字は、そこから先或いは前の世界を述べてゐる。
則(すなは)ち、「待ち伏せのような夜桜屋敷」に驚いたのはそれ以前になかつたものを見たからに外ならないからなのである。
一句を文章化すれば、
「酒を飲んだ歸りの夜道をほろ醉(よ)ひ氣分で歩いて角を曲がると、瀟洒な「屋敷」からまるで「待ち伏せ」されたかのやうに滿開の「夜桜」が目に飛び込んで來た。それまでは「夜桜」などは一切見られるやうな景色ではなかつたのに……。」
といふ事になり、
「それまでは「夜桜」などは一切見られるやうな景色ではなかつたのに……。」
までを切字の「かな」で省略した事になる。
因みに『一句二章』について少し述べれば、發句といふ文藝の『一句』は讀點(とうてん=、)ではなく、二つの句點(くてん=。)による文章(sentence)で構成されてゐて、その役目を『切字』が擔つてゐる。
「古池や蛙飛込む水の音」といふ松尾芭蕉(まつおばせう・1644-1694)の句を例にとれば、この句の「や」といふ『切字』は、
「古い池があつて」
といふ讀點の「、」ではなく、
「古い池がありました」
を句點の「。」で切る事で、
「そこに蛙が飛込んで水の音がしました」
といふ句點で締括つた事を指す。
決して、
「古い池があつて、そこに蛙が飛込んで水の音がしました」
といふ事ではなく、
「古い池がありました。そこに蛙が飛込んで水の音がしました」
といふ事なのである。
下句につく「かな」といふ『切字』の句は一章しか提示されてゐなくて、隱された一章が「かな」に要約されてゐるといふ事なのである。
二十六頁目の句。
月見草少し熱ある子を抱いて
つきみさう すこしねつある こをだいて
C♪♪♪♪†ζ┃γ♪♪♪♪♪♪♪┃♪♪♪♪†ζ┃
「月見草」は夏の季語である。
その花詞(はなことば)の「無言の愛情」といふ意味に似て、「少し熱ある子を抱い」た母親が醫者(いしや)へと急ぐ姿が句から窺へる。
「移り氣」といふ別の花詞もあるが、積極樂天的思考(ポジテイブシンキング)な方を活用すれば問題はないやうに思はれる。
句の要諦は「取合せ」であると言はれてゐるが、「月見草」から聯想される月の冷たさと、「子」供の「熱」といふ對比(たいひ)とが肝なのであらうが、そんな事よりも、この句が「て止まり」である事の方が筆者には面白く、これは連歌の「第三の體(てい)」で、「らん止まり・もがな止まり」の場合もある。
松尾芭蕉の句に、
唐崎の松は花より朧にて
といふのがあるが、發句の體ではない事が奇異に映つたのである。
今ではそれほど珍しいものではなくなつたが……。
二十九頁目の句。
怒られて男になろう雲の峰
おこられて をとこにならう くものみね
C♪♪♪♪†ζ┃♪♪♪♪♪♪†┃♪♪♪♪†ζ┃
これは社會人になつたばかりの成人した男性が仕事で失敗してどやされた場面といふよりも、小さな子供が怒られたのを見た母親が、かうして少年から男の子に成長する過程を励ましながら見守るといふ構圖(こうづ)ででもあらうか。
季語は「雲の峰」で入道雲の事である。
「積亂雲(せきらんうん)・雷雲・鐵鈷(かなとこ)雲・坂東太郎・丹波太郎・信濃太郎・石見太郎(いはみたらう)・安達太郎」
などともいふが、夏の空に聳(そび)え立つ雲の威容を山にたとへた表現で、嘗(かつ)ては「雲の嶺」とも表記した。
「男になろう」、ほらあの男性的な「雲の峰」のやうにといふ、これは取合せの句なのである。
次の句、
雪こんこんすぐ飛びたがるペルシャ猫
ゆきこんこん すぐとびたがる ペルシヤねこ
C♪♪♪♪♪♪ζ┃♪♪♪♪♪♪†┃♪♪ ♪ ♪†ζ┃
これは四十四頁にある。
この「雪こんこん」の、「こんこん」は雪が降る樣の擬音語(オノマトペ・onomatope)だと思はれるやうだが、私淑する大野晋(おほのすすむ・1919-2008)博士によれば、實(じつ)は、
「來む、來む」
と空から雪が降つて「來る來る」といふ意味だと解かれて、思はず膝を叩いた記憶がある。
窓の縁(へり)から雪の降るのを眺めてゐる猫が、思はず把(つか)まうと飛上つてゐる、愛らしい姿が眼前に浮び上がつてくる。
以上が、北村恭久子さんの句から選んだ筆者の感想である。
『Motion1金管楽器・A brass instrument 曲 高秋美樹彦』
『岡山懸 和氣の藤祭り』
二人目の作者、西村亜紀子さんの句。
初孫の泣き初めそして笑い初め
はつまごの なきぞめそして わらひぞめ
C♪♪♪♪†ζ┃♪♪♪♪♪♪†┃♪♪♪♪†ζ┃
本書の五十一頁の句であるが、未來に繋がる家族に惠まれた喜びが素直に傳はる句姿である。
別に「初孫のじやれてむづかる泣き笑ひ」とも添削例を提示してみた。
といふのも、「初」が「上句・中句・下句」のそれぞれに配置されてゐるのが氣になつたからで、敢(あへ)てこれを狙つたのだといはれれば、鋒(ほこ)を収めるに吝(やぶさ)かではない。
五十一頁目にある句。
晩鐘のかさなりあいて桃の花
ばんしようの かさなりあひて もものはな
C♪♪ ♪ ♪†ζ┃♪♪♪♪♪♪†┃♪♪♪♪†ζ┃
雰圍氣(ふんゐき)は傳はるが句意に難があり、作者に解説を請ひたくなるが、「桃の花」が音もなく「かさなりあ」つて散つてゐる場面に、「入相の鐘(晩鐘)」が遠くから響いて來る春の夕暮が思ひ浮かび、彌列(ミレエ・Millet・1814-1875)の『晩鐘』の繪を眺めるやうである。
また「かさなりあいて桃の花」は、
牡丹散つて打ち重なりぬ二三片
ぼたん ちつて うちかさなりぬ にさんべん
C♪♪♪ ♪♪†ζ┃♪♪♪♪♪♪†┃♪♪♪♪†ζ┃
といふ與謝蕪村(1716-1784)の句と想を同じうしてゐるやうに感ぜられた。
五十二頁。
私よりちょいといい女ミモザ咲く
わたしより ちよいといい
をんな ミモザさく
C♪♪♪♪†ζ┃γ ♪ ♪♪♪♪ ♪♪♪┃♪♪♪♪†ζ┃
「鏡よ、鏡! 世界で一番美しいのは誰?」
といふ女性特有の心情を句に仕立てた、洒落た作品となつてゐる。
この句は、中句が九音もあるが「女」が三連符となる事で發句の「拍子(リズム・rhythm)」として解決されてゐる。
同じく五十二頁。
シャキシャキの春のキャベツは巻かないで
シヤキシヤキの はるのキヤベツは まかないで
C ♪ ♪ ♪ ♪†ζ┃γ♪♪♪ ♪ ♪♪♪┃♪♪♪♪†ζ┃
甘藍(キヤベツ)には陳(ひね)に對して新(しん)といふのがある。
葉菜類の葉が重なり合つて球状がしつかり卷かれた状態を陳といひ、結球の卷きが淺いものを新と呼ぶが、四十年もお好み燒を經營して來た筆者にすれば、新甘藍(しんキヤベツ)は商品には向かず、この時期は陳甘藍(ひねキヤベツ)を探し廻らなければならない。
新甘藍は柔らか過ぎて、陳甘藍ほどにはシヤキシヤキはしてゐないやうに感ぜられる。
もし「シヤキシヤキ」が新鮮である事の意味で、新甘藍に對して述べたといふのであつたとしても、諾(うべな)ふにはきつ過ぎるといふものである。
見えない甘藍の中身にまで思ひを馳せてゐるやうだが、「まかないで」が現状を表したものか、願望を述べたものかまでは傳へられてゐないやうだ。
六十頁目。
ETに似た新生児ゆすらうめ
ETに にたしんせいじ ゆすらうめ
C†††ζ┃♪♪♪♪♪♪†┃♪♪♪♪†ζ┃
上句の「ET」が新奇で、しかもそれが「新生児」と似てゐるといふのである。
けれども、筆者はあの有名な映畫(えいぐわ)を觀て、「ET」を可愛いと思つた事などなかつた。
寧ろ、氣持惡いと思つた程であるが、なんと周圍(しうゐ)の若者達は可愛らしいといふ。
美の認識に狂ひが生じたのか、それとも氣持惡いけれども可愛いといふ「キモカハイイ」の部類に入るのか。
尤も、「キモカハイイ」といふ感覺などは、筆者には與(あづか)り知らぬ事である。
それに「新生児」だつて榮養が行き屆いているのか、今の兒(こ)は皺もなくツルツルで、むかしの赤子のやうに皺々で猿のやうな風貌などしてゐない。
それが「ゆすらうめ」との對比でといふか「取合せ」として配置されてゐる。
殘念ながら、成功してゐるかどうかは筆者には答へられない。
ただ面白いと而己(のみ)。
六十三頁の句。
風の道求めて陶枕持ち歩く
かぜのみち もとめてとう
まくら もちあるく
C♪♪♪♪†ζ┃♪♪♪♪♪♪ ♪♪♪┃♪♪♪♪†ζ┃
「陶枕」は本來「籐枕(とうまくら)」が古くからあつた。
別に「籠枕」もあるのだが、材料として籐や竹を使用してゐて、彈力性に富み、中空なので通氣性があつてひんやりとした感觸は晝寢(ひるね)に最適であるが、「陶枕」は當然(たうぜん)陶器で作つたからいふのであらう。
いづれにしても枕の冷氣を維持する爲には、風の力を借りた方が有効なのである。
ただ下五句が弱く感ぜられ、大きなお世話かも知れないが「風の道求める旅や陶枕」轉じて「風の道旅にも求めん陶枕」といふ二つの案を提示したい。
六十九頁の句。
満月に鍵を返しに行ったまま
まんげつに かぎをかへしに いつたまま
C♪♪♪♪†ζ┃γ♪♪♪♪♪♪♪┃♪♪♪♪†ζ┃
失禮(しつれい)な話だが、
「妻が二十年前に風呂へ行つた儘(まま)、いまだに歸つて來ない」
といふ逸話を思ひだしてしまつて、「滿月」に見蕩れてゐた爲に歸りが遅れてゐるといふ感傷的な情緒に浸り切れない。
加へて、何故、何處へ「鍵を返しに行つた」のかも氣になつて、觀賞の妨げになつてゐる。
最後に、「~たまま」といふ接續助詞で止めてゐるのは新鮮であり、それは北村恭久子さんの二十六頁目の句の「月見草少し熱ある子を抱いて」で示したやうに「て止まり」の句と同じやうな面白さは感じる事が出來る。
七十二頁の句。
満月の默っていてもいい空間
まんげつの だまつてゐても いいくうかん
C♪♪♪♪†ζ┃♪♪♪♪♪♪†┃♪♪♪♪ † ζ┃
月がものを言はなくても美しいやうに、獨りでも複數でゐても、月見には何か言葉を發する必要などありはしない。
ただ月とゐられる空間を滿喫すれば良いばかりなのである。
下五句に工夫があればと思ふ。
「我もまた滿月となる床の影」といふ一句が浮かんだ。
七十五頁の句。
外套に陽をため込んで見舞客
ぐわいたうに ひをためこんで みまひきやく
C ♪ ♪♪♪†ζ┃♪♪♪♪♪♪†┃♪♪♪ ♪ †ζ┃
病氣で入院するといふのは、それはそれは退屈なものである。
特に手術後の經過(けいくわ)も良く、院内を歩けるやうになつてからは手持無沙汰にやり切れなくなつて仕舞ふもので、それはさうなつた經驗者にしか解らないだらう。
筆者などは多趣味のお蔭で、DVDや個人用電腦 (パソコン)を持込んだりして病室は書齋と化す有樣であつた。
無論、病院からの許可を貰つてゐたから事なきを得たのであるが、多くの患者は嚙み殺す欠伸(あくび)を數(かぞ)へる羽目になる。
病院は個室ならば問題はないが、相部屋の場合に運良く窓側でない限り、外の景色を眺める事が出来ない。
ことほど左樣に無聊を託(かこ)つもので、況(ま)して味氣ない食事の事を考へると、入院してゐる時の愉しみは見舞客の來訪ぐらゐのものである。
その「見舞客」が冬空の弱弱しい太陽の陽射しを浴びて、入院してゐる彼女の爲に歩を運んでゐる。
笑顏をふりまきながら病室の扉を開けて「外套」を脱ぐ。
すると「見舞客」の體温(たいをん)と共に「ため込ん」だ「陽」のぬくもりが病人の周(まは)りに注がれるやうである。
それは何よりも見舞の品物として嬉しかつた事であらう。
以上が、西村亜紀子さんの句に對(たい)する拙(つたな)い感想である。
『Motion1(Mirror) &(Substance) 曲 高秋 美樹彦』
『伊丹市 柿衞文庫』
次は三人目の作者。
最後の作者は室展子さんで、彼女だけが歴史的假名遣(れきしてきかなづかひ)で表記されてゐた。
本來、和歌や發句は歴史的假名遣で表記されるものだと考へてゐる筆者であるから、我が意を得たりと氣持良く鑑賞出來た。
ただ、歴史的假名遣は明治政府によつて制定されてもので、その範を『古事記・萬葉集』等の時代の歴史的な發音及び表記に基く故に、さう呼ばれてゐて、それ以降の『平安・鎌倉・室町・江戸』期には表記が一定してゐない憾(うら)みがある。
八十四頁目の句。
色町の先は寺領やかげろへる
いろまちの さきはじりやうや かげろへる
C♪♪♪♪†ζ┃γ♪♪♪♪ ♪ ♪♪┃♪♪♪♪†ζ┃
「色町」とは「色里・遊郭・花柳街」とも言はれ、人々が集まつて遊女屋や藝者屋で遊興する場所である。
煩惱(ぼんなう)にまみれた地域のその先には寺院の所有する領地があつて、恰(あたか)も結婚場が葬儀場を兼ねたやうなもので、迷ひから悟りへと地續きとなつてゐる。
「色即是空 空即是色」
といふ言葉の「色」が「色事」と誤まつて解釋(かいしやく)され、「空」が虚しいと取違へられるに及んで、女色(ぢよしよく)に迷ふ戒めの言葉と誤解された。
昭和三十一(1956)年に賣春防止法が施行されてからは、建前は春を鬻(ひさ)ぐ女性やそれを管理する者は存在しない筈であるが、さうでない事は諒解されてゐる。
情緒纏綿とした「色町」の風情も今は昔となり、かすかに陽炎に搖れてゐる寺院を先方に意識しながら、春のひと時を過ごしてゐるといふ句意であらうか。
八十九頁。
咲きながらもう散つている桜かな
さきながら もうちつてゐる さくらかな
C♪♪♪♪†ζ┃♪♪♪♪♪♪†┃♪♪♪♪†ζ┃
恐らく誤植なのだらうが、中句の「散つている」の「い」が「ゐ」になつてゐない。
氣にはなるが、それよりも「花は櫻木、人は武士」といふ優れてゐるものを表現した慣用句から、その根柢(こんてい)には潔さを表はしたと思はれる喩(たと)への方が大事だとでもいふやうに、「咲きながらもう」潔く「散つている桜」を、さうであるが故に愛(め)でてゐるのだといふ一句である。
當然(たうぜん)、
「少し前までは櫻の花などは小さな蕾だつたのが、一氣に咲いたかと思ふともう散つてゐる」
といふ、
「少し前までは櫻の花などは小さな蕾だつたのが」
までを「かな」で纏めたのはいふまでもない。
八十九頁。
囀りの太古の森へ溶けゆけり
さへずりの たいこのもりへ とけゆけり
C♪♪♪♪†ζ┃♪♪♪♪♪♪†┃♪♪♪♪†ζ┃
この句は、姿の見えない鳥の「囀り」が「太古の森へ」と「溶け」込んでゆくやうだといふ状況を表現した一句であるが、さうであるならば、
「しづかさや岩に沁み入る蝉のこゑ」
といふ芭蕉の句と同じ境地を詠んだものであらう。
屋久島にでも行つた時の句だと言はれれば、納得。
九十六頁目の句。
要件のすぐ片付きぬ冷奴
えうけんの すぐかたづきぬ ひややつこ
C♪♪♪♪†ζ┃♪♪♪♪♪♪†┃♪♪♪♪†ζ┃
連合ひとでも晩酌をしようと思つて、冷奴を洋卓(テエブル)の上に置いたその時、呼鈴が鳴つたので玄關へと向つた。
どうせ回覧板でも廻つてきたのだらうから、直ぐに「要件」は濟むので先に一杯やつてゐてと配偶者へ傳へる。
冷たい食感を殘したまま、一緒に食卓を圍めるからといふ一句か。
九十九頁目。
祖父の地の風匂ひ来る墓参かな
そふのちの かぜにほひくる ぼさんかな
C♪♪♪♪†ζ┃♪♪♪♪♪♪†┃♪♪♪♪†ζ┃
久し振りに訪ねた「祖父の地」で、目的の先祖の「墓參(はかまゐ)」りをしに來たら、何處からか「風に」乘つて線香の「匂ひ」が漂つて來た。
もう誰かが「墓参」に來てゐる律儀な地元の人の行爲に、都會に出てたとはいへ、親不孝ならぬ先祖不孝を平然と過ごして來た自身の薄情さに、慄然として仕舞ふ。
さういつた光景が浮んできた。
百頁目の句。
天の川人は何処へ行くならむ
あまのがは ひとはいづこへ ゆくならむ
C♪♪♪♪†ζ┃γ♪♪♪♪♪♪♪┃♪♪♪♪†ζ┃
「天の川」のやうな宏大な宇宙を見上げてゐると、時にちつぽけな自身の存在を自覺して、哲學的な命題に浸りたくなつて仕舞ふものである。
「ならむ」とは、斷定の助動詞「なり」の未然形に推量の助動詞「む(ん)」のついたもので、「だらう」といふ推量の意を表はしてゐるのだが、にしても觀念的に過ぎはしまいか。
それにも拘はらず、筆者はかういふ問ひかけが好きである。
百六頁目。
しばらくは夕日の赤き棗の実
しばらくは ゆうひのあかき なつめのみ
C♪♪♪♪†ζ┃♪♪♪♪♪♪†┃♪♪♪♪†ζ┃
全ての時間はうつろひ行くものである。
あの美しい夕日でさへ、誰にも地平線にとどめておく譯に行きはしない。
「棗」はクロウメモドキ科の落葉喬木で中國原産だと辭書(じしよ)にある。
高さは十米(メエトル)にも達し、日本に渡來したのは古く、庭木として親しまれてゐるのだが、薔薇と同じやうに枝に棘があるので、魔除けとか防犯の役目も兼ねてゐたのかも知れない。
尤も、これは私見でしかないが……。
ただし、「夕日」と「棗の実」の取合せの意味が不明である。
實景(じつけい)に立合つていないゆゑの感想なのだらうが。
百七頁目。
ふくろふの片目を開く闇夜かな
ふくろふの かためをひらく やみよかな
C♪♪♪♪†ζ┃♪♪♪♪♪♪†┃♪♪♪♪†ζ┃
餘(あま)りの「闇夜」に「ふくろふ」でさへも「片目を開く」といふ意味なのか。
極めて觀念的な作品であると思はれる。
百九頁目。
マスクしてこの世のものといへぬ声
マスクして このよのものと いへぬこゑ
C♪♪♪♪†ζ┃♪♪♪♪♪♪†┃♪♪♪♪†ζ┃
報道番組などで情報提供者が特定されないやうに音聲(おんせい)を變(か)へる事があるが、それと同じやうに「マスク」も似たやうな効果が得られる。
さういつた人から聲をかけられても、顏も判別し難(にく)いので不安な思ひに驅られてしまふ。
「私だよ」
と言はれて「マスク」を外され、知人だと解つて初めて安堵するのである。
さう言つた經驗(けいけん)は、誰にでもあるでせうといふ一句なの歟(か)。
百十二頁目。
友の来て家の膨らむ女正月
とものきて いへのふくらむ をんな
しやうぐわつ
C♪♪♪♪†ζ┃γ♪♪♪♪♪♪♪┃♪♪♪ ♪ ♪ † ζ┃
「女正月」とは一月十五日の事で、元旦からも多忙な女性がこの頃になつて漸く手が空(す)いて年賀に出向いたり、慰勞の爲に女性達だけで集まつたりする事からいふが、一月一日を「大正月」といふのに對して「小正月」ともいふ。
この句では、中句の「家」が「膨らむ」といふ表現が秀逸だと思ふ。
序(ついで)に言へば、語を整へる爲に下五句を『女正月』を「をんなしやうぐわつ」と讀まず、「めしやうぐわつ」としたい處だが、それはやり過ぎといふものであらう。
因みに「大正月」を男正月ともいふ。
百十三頁目。
寒卵命のもとは柔らかき
かんたまご いのちのもとは やはらかき
C♪♪♪♪†ζ┃♪♪♪♪♪♪†┃♪♪♪♪†ζ┃
「寒卵」とは寒中に生んだ鶏卵の事である。
新しい卵の殼は弾力に優れ、なかなか割れない。
言はれる通り、「命」とはしなやかな柔軟性に富んでゐるものなのかも知れない。
赤子を抱くやうに、「寒卵」の觸感まで傳へようとした句でなのであらう。
百十四頁の句。
ピザを焼く竈あかあか冬の雨
ピザをやく かまどあかあか ふゆのあめ
C♪♪♪♪†ζ┃γ♪♪♪♪♪♪♪┃♪♪♪♪†ζ┃
この時代の都會に「竈」が自宅にあるなんて、非常に驚きである。
若しかすると商賣なので、「竈」があるのかも知れない。
この句は「竈」の「あかあか」と燃えてゐる色と、冷たい「冬の雨」の暗い色との取合せが上手いと感ぜられた。
以上、人樣の作品に意見を述べるといふのは、骨が折れるばかりか汗顔の至りでしかなく、幾度か筆を擱(お)いてはまた書くといふなどを繰返して、つひに三年といふ月日が流れてしまつた。
この間、トミイさんの「マイカラオケコンサアト」の編輯(へんしふ)作業をしなければならなくなつて、作句ばかりか作曲や研究論文、自身の身内の映像編輯さへも時間を割く暇(いとま)を失つてしまひ、全てに對して動因(モチベエシヨン)が掻立てられなくなつてほとほと弱つてゐる。
筆者の殘り時間も餘り多いとはいへなくなつたので、これを機に、自分のしたい作業の方へ比重を移して行きたいと考へてゐる次第である。
ここに書いたものは、筆者の獨斷と偏見に滿ちた書評であるとご理解戴きたい。
要らざる事を述べたとお怒りの三人の作者には、もし不快な思ひを與(あた)へたとすれば、お詫びを申し上げたい。
平成三十(2018)年四月二十九日(日)店にて 著者記す