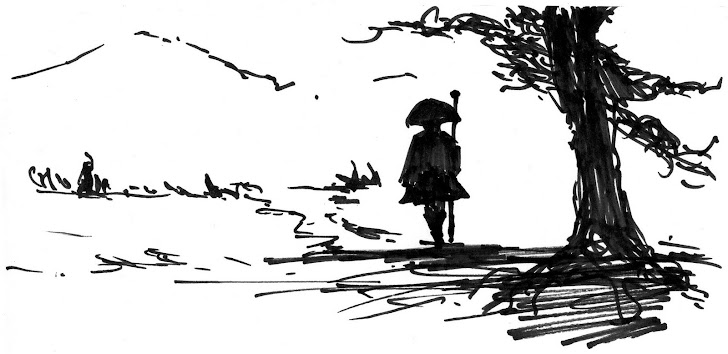第二發句集
(Second collection of Hokku poetry)
(Second collection of Hokku poetry)
『草の笛(Leaf whistle)』
この作品を讀む時に、この音樂を聞きながら鑑賞して下さい。
これは自作(オリジナル)の
『Motion1(Mirror) &(Substance) 曲 高秋 美樹彦』
といふ曲で、YAMAHAの「QY100」で作りました。
映像は伊丹にある、
『柿衞文庫』
へ出かけた時のものです。
雰圍氣を味はつて戴ければ幸ひですが、ない方が良いといふ讀者は聞かなくても構ひませんので、ご自由にどうぞ。
發句集(Collection of Hokku poetry)『草の笛(Leaf whistle)』は筆者の二作目の作品である。
一九六六昭和四十一丙午(ひのえうま)年から、
一九七〇昭和四五庚戌(かのえいぬ)年までに詠んだ句を纏めたものである。
拙い作品が多いながら、捨て難く思つてゐた記憶がある。
ご鑑賞下さい。
一九六六昭和四十一丙午(ひのえうま)年から、
一九七〇昭和四五庚戌(かのえいぬ)年までに詠んだ句を纏めたものである。
拙い作品が多いながら、捨て難く思つてゐた記憶がある。
ご鑑賞下さい。
序
予に年古(としふ)る歳月はあれど、幼き心のいづこにも見えざり。
斯かる今も哀しく世を厭(いと)ひければ、軈(やが)ての日にも幼き心を得られざらんことを、予は覺悟してゐたり。
これ何人(なんぴと)と雖(いへど)も、予に安らげる幼き心の境地、與(あた)ふるを能(あた)はず。
然(さ)れば、いつか予の口より出づる詩歌以(も)て、せめて幼き心の世界を正月に當(あた)り、たましひを込めて創らんと思ひついたり。
これを不肖なる予は、魅了されたつが如くに、いざ一年(ひととせ)の建前とせん。
ひとり世に百まで手毬つき唄ふ
時に昭和四十五庚戌(かのえいぬ)年正月朔日未明
第二發句集『草の笛』
題 言
かなたより雲ふるはせて草の笛
正 月
元旦――。
予は三重縣度會(わたらひ)郡古和浦にこの身を置けり。
古和浦は繼母の里にあり。
予を含めたる父と繼母と弟二人の家族は、昨年の師走の三十日に大坂を出でて四、五時間の後、古和浦に着きぬ。
古和浦には七十歳になる繼母の兩親が、廣き屋敷に閑として二人だけの生活を營めり。
古和浦が繼母の親戚はいたく多かり。
その數の多き故に、予はこの村は親族の寄り集まりにて出來たる村かと思ひし程なり。
然(さ)れば、村人の家族及び予に對せし世話振りは、最早他人の影を拭ひ去りたるも同然といへる感あり。
これ素朴なる人柄ゆゑに相違なき、と感じたるも甚だしき。
都會には失せたるものにあり。
正月を古和浦にて過すは、予の二度目の經驗なり。
一度目は二年前に來たりて、山火事を見たる故によく覺えてゐたり。
この地は海と山とに壓(お)されてあり。
伊勢柏崎より來たれば、バスにて一時間の乘車にて峠を二つ越えて來たる所なり。
古和浦の地は正面に空と海の開けてあり、その背後は餘りに山多くして峠の數を知るも能はず。
かくて二度目の訪問となるなり。
正月に無聊(ぶれう)を託(かこ)ち、眠るばかりなり。
また、この地に遊ぶ所は全く無之けれども、風流を解せし者にあれば、頗(すこぶ)る有難き場所と思へり。
更に、人の少なきを以(もつ)て思ふれば、かかる地は無比に近きと云へり。
海空がひとつに見ゆる三つの朝
二 日
二日。
生を受けてより幾度も正月を迎ふれど、予は未だに正月の何が芽出たきかを不知。
日數を重ねしばかりと思ほゆ。
天地極まらず、予の生ある限りは、如何(いかん)ともこの氣持のやり場なきを知りぬ。
斯くも人に疎まれ、猶更、正月に笑ひを知り得ずして、人の倍も眠り、頭痛くなりて年を重ねる事を憚れず。
かくあれと上り双六ひと年(とせ)に
然(さ)れば双六はせねど、人の世に「上り」あるを予は願ふなり。
その「上り」の死に非ざる事をも。
三 日
三日。
目覺め惡しくして茫然とすなり。
頭の中に何もなくて身體(からだ)重し。
我が獏は夢そのものを喰らひけり
獏は惡夢のみを喰ふに非ず。
予に於いては獏が爲に、夢は見られるものに非ず。
獏は隔てなく、哀樂ともに現實の夢を喰らひたり。
四 日
暖かき心地は格別と申せし新春なり。
外は風のある可くも見ゆるが、茶を呑みし予には何しようものか。
父は弟と午後の釣りを樂しみたると繼母の言ふ。
予は近き廣場に集まりたる幼兒の聲を、聞かんともせずに耳に受けたり。
手毬唄覺えた年も二十歳かな
不圖、出でたる句なり。
閑とせし家の中ゆゑ、予の心を隅に小さくあるなり。
五 日
餘りの寒さに目の開くなり。
今年の正月は朔日より暖かきゆゑ、それのみを樂しみをれど、予の氣がつけば、窓の外に雪のチラと降りたるを見る。
初雪やまづ一番に鼻の上
けふは大阪へ歸る日にあり。
早朝に古和浦を立つと雖も、午後になりたるを予が家の慣例とす。
風強く、空を見遣るも、雪荒るるは明らかなる可し。
予らは古和浦の人々と別れてより、父の運轉したる自動車に乘りて大坂へと向ふなり。
初雪や道二筋に分かれけり
鈴鹿峠に近くなりて、雪、形ありしものを虚像と化し、元の姿を止どむる所を不知。
鈴鹿峠に到りて、自動車にタイヤチエエンを必要とす。
山道の端々に轉落したりし幾つかの車を認め、あるいは岩壁にぶつかりたる車もあり。
雪の中を走りたる予らが車の車體は氷りつきて、氷柱をも見えたり。
雪は勢ひを弱めずして、強くなりたるばかりなり。
その情緒風景は絶なれど、ひとたびこの寂たる樣の恐ろしさを秘めたるを見るは容易(たやす)きかな。
降り初むる雪のさだめも風まかせ
見渡せば林を前に雪吠えぬ
峠より雪にけぶれる街の影
鈴鹿峠を越ゆれど、雪、いまだ斜めに流れたり。
車多くして、田畑に轉落したるも見るあり。
予が父はなにを恐るるに足らん、と車を從はすなり。
雪降りて空暗くあれども、いつか陽の出でたるを見る。
今、越え來たる鈴鹿峠を振返りて見やれば、
太陽にひかり散り初む峰の雪
太陽と雪のまぶしき刹那かな
降りしきる雪や人なき道の上
雪けむり人の住みたる情けゆゑ
うつせみの街しろくして雪の影
かかる雪の激しき街なれば、人の姿は絶えて、その街の靜かなりしたたずまひは、いにしへの心を偲びたるが如し。
予は、この街に如何なる由緒のありしかを不知。
また、この街の名は雪に埋れたるが如く、予に知らしむる術のなかりしぞ、と早くも街を過ぎ行くなり。
雪野路を汽車の行手や明渡り
入相の鐘の音洩る春の雪
雪の街外れて人に逢ひし息
例外の墓場もやがて銀世界
戒名も埋れて見えず雪の外
雪降りて探られさぐる佛心情
寺のある街にて、とは予の空想にある。
空想の雪降るごとにふるごとに
この句はむしろ一茶的と言へる句にあり。
初雪や命ふるへて湯を啜る
車の中にて走り去る景色を眺めもせず、水筒に入れてありし湯をひとり呑みたり。
寒さなほも甚だしき。
雪觸れて消えて命の幾許ぞ
やがて甲賀の忍者屋敷なども見えたり。
浪漫に富みし國なり。
夕映えや雪の甲賀へ獨り消ゆ
雪や春空想の句を五七五
泉の如く發句の湧き出づる一日なり。
さて、栗東に來たれば雪もまばらにて、名神高速道路に入りたれば雪に別れんとするのみ。
かくて大坂へ車を走らせるなり。
大坂に着いたれば眠るばかりなり、と車の中にて寢てゐたり。
六 日
一日の大半を寢て過し、なにも言へずにゐたり。
冷える部屋の何に例へる術もがな。
安心も溜息まじり浪花かな
七 日
何を喰へといふや。
をかしくも人はなにをか喰ふ日と思ひをる。
予は友人の高橋氏と珈琲を飲むのみにあり。
人の日の深夜喫茶のひそひそと
高橋氏と別れて部屋に戻り、一人身ゆゑに粥を喰ふ當てなくて、かの友の置いて行きたる林檎を喰ふなり。
九 日
作年の暮に辭(や)めた會社へ手紙を書くなり。
予は世話になりたるを理不盡にも退社したるなり。
迷惑甚だしきと思ふ故、申し譯なさに詫びること頻りなり。
あらたまの年に皺寄す去年(こぞ)の罪
古和浦より五日に歸り來たれば、年賀状多く有之。
然(さ)れば、その返事をご苦勞にも書き始めたり。
めでたさも項垂るるほど春の外
十 日
漸く手紙を書き終へたり。
いま午前三時なり。
一秒過ぐるごとに一年もかくあると思ふ悲しさ。
古びたる後家の住ひの蜜柑かな
十一日
不相變(あひかはらず)深夜になりても眠らぬ氣儘を實行してゐたり。
けふもけふとて目を覺ましたるは、午後の三時にあり。
幾ら慣れたるとは雖も、流石に予も頭痛し。
夜行蟲ねむりも醒めぬ冬の晝(ひる)
「夜行蟲」は夏の季語なれど、「夜行性」と改むるを良とせず、季節外れを意とせんか。
彌生(やよひ) 某日
某日、その日、大坂に珍しくも雪の降りたるなり。
都會のビルの間に降る雪の、また別の美しさを見たる思ひなり。
わが心ひとつへだてた外に雪
雪舞ふや窓をへだててもの思ふ
はるかなる雪や都會にもの申す
遠くより來たれる雪も白さゆゑ
雪止みてまた降り出しぬ町の色
雪舞ひて戀に燃えたる人を見つ
霏々として町泣き濡るる雪の中
春の雪笑へぬ男となりにけり
彌 生 三十日
三十日、雨の降りたり。
かなしみのとほり一遍春の雨
卯 月 六日
六日、讀賣新聞大阪本社へアルバイトで働き出してより、既に一箇月が過ぎたり。
滝充宏氏と知遇を得る。
それゆゑにおどけんとする春思かな
春愁やおどけんとするそれゆゑに
蝙蝠や人にかはりて泣くゆふべ
關聯記事
蝙 蝠(かうもり)
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=52750695&comm_id=4699373
卯 月 某日
日時不明なり。
花ひとつかぎろふ中に舞ひにけり
そつとしておくものにありすみれ草
菜の花や陽の當りたるひと處
山ありき川ありき村春なりき
うつうつと靄あやしげな山の影
花曇り死の影蹈んで墓地の中
皐 月
戀よりも生さへ疲れ果てた春
悲しみはつもるほどあり春の闇
胸の蔭痞(つか)へたままに春の果
なにくはぬ顏してをれど春も暮
足るといふ事まだ知らぬらし春の暮
人は上ばかりを見てゐたり。
鬱として不如帰啼き明け初むる
四日、わが誕生日に新鮮さはなし。
されば島袋氏に贈りたる句をひねりたるのみ。
よくもまあ五月に生けるしぶとさよ
五月雨に澄みたるものが濁りけり
夏立てばまた人の目に戀ふる色
夏にまた悲しみひとつ戀の色
夏立てば悲しくもまた人戀ふる
ことさらに紅が目に入る麝香撫子(カアネエシヨン)
あぢさゐの匂ふが如き手紙かな
匂はぬ花なればこそ句に詠まん。
憂鬱な涙にひかる夏の艷
水無月
夏の身が罪を背負ひて影細し
夏來ればもの吐き出して死にたしも
ひんやりと白雲を追ふ死への道
茫々と人の道あり夏の雨
日輪をひんやりと見し夏の朝
堂々と、
おくびにも世を果敢なみぬ夏の山
ひとすぢに夏の燈臺白き道
夏立つや眦(まなじり)喝と世を見やれ
夏の山思ひしづかや木々の樣
炎天やおくれとるまい己が道
まだ暑き晝(ひる)に最後の戀燃えて
ヴイイナスや頭の中に白き泡
十九日、この二句は山田祥子女子の誕生日に贈りたりものなり。
色紙に書きたれども、十九歳を二十歳と勘違ひしてゐたり。
白鷺のその白くあれ白くあれ
梅雨暗くまだ見ぬ人に逢ひたしも
文 月
耕しつ夏の荒れ道歩みけり
十六日、大西氏と京都の祇園祭に行くなり。
人の甚だしき樣を見て、
外人のおどろきもせぬ祇園かな 賢二
と大西氏が詠むなり。
これは祇園祭の世界的になりたる所以(ゆゑん)と講釋を附けるなり。
扨(さて)、余はと言はばいふを待たず、詠みも詠んだり。
いきいきと祇園の道の續きける
活きいきと祇園や人の道ばかり
夢の道歩きつかれた祇園かな
塵勞をふと忘れたる祇園かな
塵勞により疲れたる祇園かな
余と大西氏とは夜中まで過してのち、大坂へ歸りたり。
廿日、大西氏と自動車にて琵琶湖を一周するなり。
蜉蝣の透けて膝元とほりけり
今日さへ學校に行かば明日より夏休みにて、その爲に早く歸らんと琵琶湖大橋を横斷する途中にて速度違反の疑惑ありて捕まるも、運よく警告のみにて難を免れて學校にも無事著(つ)きたり。
二十四日、ついでに生きたる者にあれば、またついでに死ぬる事も道理といへるものにある歟(か)。
河童忌やわれはついでの命かな
葉 月
秋立つや誰も見つけぬ水の色
やがてまた悲しみさそふ秋の旅
長 月
立止まり立止まりつつ秋の空
雙眸のなんとはなしに秋の色
空ありて傳説の樹が月の中
戸を開けて入り來たりた秋の顏
夕陽より生れ出でたる蜻蛉かな
たましひの行きつくところ秋の暮
いと高く高くあれ空と夢
松原女史の誕生日に贈りたる句なり。
神無月
十九日、名古屋へ行く途中の汽車にて。
なにいゑに耳鳴りのする秋の夜
ひいと泣く秋もおはりの旅の風
しあはせのチツチと耳の側で秋
この世界に共に生きる蟲の聲あり。
秋は風仕方がなしに街の外
人の世の愁ひを越えて天高し
世が世ならせめて柘榴にあやかれん
確かヴアレリイ(1871-1945)の言葉に「自らの叡智に割れてしまふ」と言はれた柘榴(ざくろ)を見て。
秋の雨降つた證(あかし)や塀の色
秋風やわがたましひの行き處
清き月あまりに添はぬ心かな
露の世はわれを忘れて去り行かん
余はこの秋に、自身が一體(いつたい)どれほど信じられる事が出來得るかを試して見る心算(つもり)なり。
他の人も信じられずに秋の下
他の人の信じられない秋の聲
さうしてこの秋はつひに、
他の人が信じられぬまま秋の暮
霜 月
續く限り星を數へて秋果かな
負け犬のしぐるる
雨にひとりぼち
ひとつ身のわれは鮑(あはび)ぞ行くや秋
芭蕉翁を偲んで。
六日、予が一生に何があるかと思ふ悲しさ。
予は文章を書き殘すのみ。
何をかを求めて文を綴るのみ。
兒の産めるをんなよ我は秋惜しむ
昔ほどたれも通らん冬の道
冬の日や頼るものなく暮しけり
冬の陽や鬢をかすめて沈みけり
約束も延ばしのばしで短き日
冬雲やまるで空より上に浮く
木のごとく動かず鳴かず冬の鳥
みづどりやわれは岸邊で見るばかり
水鳥は岸邊へ上がつて來ようとはしなかつた。
陸地の住みにくさを知つてゐるのだらうか。
極 月
九日、「今晩は」と予に訪ねる人のあり。
誰かと問はば「漱石ぞ」と答ふ。
年一度來たりた客も漱石忌
終電車待つ手持ち無沙汰や驛寒し
人徳の厚きといはれし人が鎌鼬(かまいたち)
むかし死んだ狂ひをんなが冬の月
人なくも狂女の聲が冬の月
この第一句目はもつと直接的な表現だつたが、かくは改めたり。
部屋の湯氣に窓邊のをんなくもりけり
降誕祭(クリスマス)祈る氣持もさらさらに
思ひ出の手袋ひとつ左だけ
ひとつの手袋を彼女と分けて裸の手をつないだり、あるいはそれぞれの互ひのポケツトに手を入れあつて物語りせんとの空想なり。
後 記
この作品は、始め「手毬唄」と題してゐた。
それが「草の笛」と變つた理由は簡単である。
「序」にも書いてある通り日記風にするつもりが、正月も十一日で筆者が書く事を抛棄してしまつたので日記が續かなかつたからである。
それでも發句だけは書き留めておいたから、なんとか纏めることが出來てこんにちの形となつたのである。
要するに、それに當つて題名をその儘にしておくのは、筆者が良心の呵責に耐へ切れなかつたといふだけの事である。
發句の創作日も不明で纏めるのに苦勞をしたが、今囘の發句集は本當に發句だけの句集となつてしまつた。
けれども、この句集の中に自信の作は可成ある。
例によつて人を薄氣味惡がらせたり、恐ろしくさせたりする雰圍氣の句も含まれてゐて、それ以外に今囘は大らかな自然も詠んでゐる。
兔に角、筆者としても新しい言葉を探すのに懸命であるが、なかなかうまく行かない。
この作品は昭和四十五年度の作のもので、纏めるのに實に四年の歳月を費やしてゐる。
しかし、決して筆者はサボつてゐた譯ではない。
筆者も人間である以上、食事もすれば睡眠もする。
生活をする爲には金錢を得なければならない。
さうすると、自ずから働かざるを得ない。
その間を縫つてものを書き、まづその前に着想するのだからそれほど閑のあらう筈がない。
第三集は『霧鐘』といふ題がついてゐる。
この題名が變るかどうかを樂しみにされては適はないが、それがどうなるか筆者にもそれは解らない。
案外樂しんでゐるのは、筆者だけかも知れないが……。
一九七三昭和四十八癸丑(みずのとうし)年葉月二日午前六時