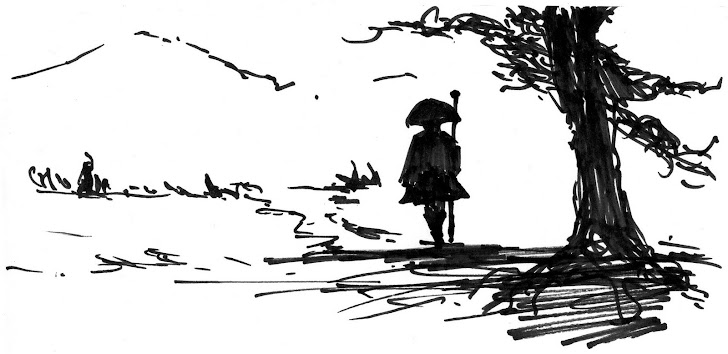連歌の作法 Early Japanese poetry Renga form method
その一、
その一、
この作品を讀む時に、この音樂を聞きながら鑑賞して下さい。
これは自作(オリジナル)の
『Motion1(Mirror) &(Substance) 曲 高秋 美樹彦』
といふ曲で、YAMAHAの「QY100」で作りました。
映像は伊丹にある、
『柿衞文庫』
へ出かけた時のものです。
雰圍氣を味はつて戴ければ幸ひですが、ない方が良いといふ讀者は聞かなくても構ひませんので、ご自由にどうぞ。
その一、連歌の作法
連歌を誰もが樂しめるやうにする爲に、これから暫(しばら)く連載したいと思ふ。
が、連歌は、俳諧の時に「連句」とも稱(しよう)して多く用(もち)ゐられるが、しかし、この名稱は明治期の人が、芭蕉を尊敬する餘り、勝手に「連歌」と區別したもので、芭蕉自身は、
「俳諧・俳諧の連歌・連俳」
と述べたと、弟子の書物の中にあるばかりで、それは「正風」を「蕉風」と言ひ換へたのと同じやうなもので、感心すべき事ではないと思はれる。
そこで和歌の『連歌』とは、
短歌の「上句・五七五」と「下句・七七」
を別々の人が詠む、といふ事ぐらゐは知つてゐるだらう。
しかし、連歌は、
「獨吟」の場合だと、
「五七五」と「七七」
を獨りで詠み續け、
「兩吟」の場合だと、
「五七五」
を一人が詠んだら、
「七七」と、次の「五七五」
をもう一人が詠み、再び、
「七七」「五七五」
と呼んで行くので、
「五七五」「七七」
を別々に詠む事が出來ないので、必ずしも交互に詠む事を基本とするものではない。
以上の事を理解する爲には、もう少し詳しい解説が必要だから、今囘は先づ連歌の句數について述べて見たいと思ふ。
連歌には、「上句・五七五」と「下句・七七」を合せて「百句」になるものを、
『百韻連歌』
といふ。
その半分の「五十句」のものを、
『五十韻』
といふ。
さうして、「四十四句」で一卷とするものを、
『世吉連歌(世久連歌)』
といふ。
また、「三十六句」で一卷とするものを、
『歌仙』
といふ。
芭蕉以降は、
『歌仙』
の形態が多く見られ、初めに述べたやうに、俳諧といふ滑稽を目的としたものは、和歌も傳統を受け繼いだ幽玄で優美さを重んじた純正な連歌を、
『有心連歌(うしんれんが)』
といふのに對して、
『無心連歌(むしんれんが)』
と言ひ、『無心連歌』の作法を、次から『箕面吟行』の中の、『歌仙』を實例にして詳細に考察したいと思ふ。
參考文獻
岩波講座「連歌及び連歌史」 山田孝雄 岩波書店
連歌の作法 その二
今囘は、約束通り例を示すが、それに當(あた)つて、『箕面吟行』では、大蔵司宏氏との「兩吟」といふ事で發表したが、それは捏造(ねつざう)であつた事は、「後書(あとがき)」で述べたので、作者三人で詠ずる「三吟」といふ一座の形で述べたいと思ふ。
敢(あへ)て「近江派」と呼ぶ程のものではないが、
甲子
乙女
丙内
以上の架空の三人で、「三吟」を興行したいと思ふが、次にその『歌仙』の全句を掲載する。
呼 稱 季 解 説 實 例 作者
1初 折 發 句 秋 夕暮の目にせまりくる瀧紅葉 甲子
2一の折 脇 秋 途切れし音に秋は去りつつ 乙女
3 第 三 雜 瀬を渡り足を拭へば目を閉ぢて 丙内
4初 面 第 四 雜 啜る湯呑に澤庵の味 甲
5 平 句 冬 月の座 ひと聲に素振りをくれて寒の月 乙
6折 端 以下同 雜 誰も咎めぬ夢なればこそ 丙
裏移り
7初 裏 冬 振袖を着せたきままに年越して 甲
8 春 枯木も花を身にまとひ 乙
9 春 春火事にもろ肌を脱ぐめ組かな 丙
10 雜 刺青見せて裁き輕やか 甲
11 戀の句 雜 俎の鯉を料理の流れ板 乙
12 冬 温もり殘す蒲團抱き締め 丙
13 雜 月の座 三月越し二階貸したる人いづこ 甲
14 雜 名乘り上げれば御曹司とかや 乙
15 春 許されてわが世の春を御散財 丙
16 春 驕れる人のうれしかるらん 甲
17 春 花の座 無斷にても難色もなし花の宴 乙
18 雜 小言が來ても聞 けぬ芳一 丙
折 立
19二の折 春 行く春の重たき琵琶に腰拔かし 甲
20 雜 明方豆腐を角で買ふなり 乙
21二の表 戀の句 雜 召上がれ戀はなま物おはやめに 丙
22(名殘 戀の句 夏 蝉も螢も老いにうるさし 甲
23の表) 戀の句 夏 宵宮の祗園囃に馴染客 乙
24 戀の句 雜 主が命と送る後朝 丙
25 雜 べろを出し惚れた晴れたも藝の内 甲
26 雜 口を開けたら閻魔驚く 乙
27 雜 金次第とは云へ行けるも地獄だけ 丙
28 雜 笑ひ飛ばして住めば都か 甲
29 秋 月の座 身じろぎて男が月に吠える影 乙
30 雜 野の虎でさへ元は詩を詠む 丙
裏移り
31二の裏 秋 旅に寝て濡らす枕も袖の中 甲
32(名殘 冬 身に沁む冬の主の情 乙
33の裏) 雜 因縁の昔語りに夜も更けぬ 丙
34 春 漸く明けた春はやまぎは 甲
35 春 花の座 をかしさに一歩蹈み出す野邊の花 乙
36擧句 春 日に從ひて向日葵の咲く 丙
以上が「歌仙一卷」といふ譯である。
連歌の作法 その三、
連歌には作者の順番を決めて詠む「膝送り」と、迅いもの勝ちで出された句を取上げる「出合(であひ)・出勝(でがち)」といふものがあり、數名の場合は「膝送り」に從つてゐる。
これら前囘の句の解説は次囘に譲るとして、連歌や發句は小説などの散文を書く場合にも役立ち、井原西鶴がその良い見本となるだらう。
それと「發句」と「平句」の差が、連歌から獨立した場合の發句と川柳の違ひとなつて、これも『發句雜記』で述べるから詳しくは説明しないが、連歌の「發句」は人を訪ねた時の挨拶で、季節が入るのは手紙の冒頭の時候の時と變らず、
「客發句(友人からの手紙)・脇亭主(受けてからの返信)」
などと言はれる事でも、それが知られるだらう。
第一句は、『發句(ほつく)又は立句(たてく)』と言ひ、
第二句は、『入韻(じふゐん)』とも古くは言つたが、普通には『脇』と言ふ。
第三句は、『て止まり・らん止まり』の句で、『第三』と言ひ、
第四句は、『第四』で、
それ以降は呼名がなく、『平句』と言ふ。
全體は、
『六(初折)・十二(初裏・名殘りの表)・十二(二の折)・六(二の裏・名殘りの裏)』
の四つに區切られてゐて、
『序破急』が、
『「六(序)」・「十二・十二(破)」・「六(急)」』
このやうに當てられ、各々(おのおの)に詠まなければならない規則があり、
その一つは、『座』といふものであり、
今一つは、『神祇(しんぎ)釋經(しゃくきやう)戀(こひ)無情(むじやう)』と言ふものである。
『座』といふものは、
『月の座』と『花の座』があるが、
「初折」には『月の座』が五句目、
「初裏」には七句目に『月の座』と十一句目に『花の座』、
「名殘りの表」には十一句目に『月の座』があり、
「名殘りの裏」の五句目に『花の座』がある。
『神祇釋經戀無情』は、發句の場合はどれを詠んでも構はず、
『戀』が「初裏」の五・六句目、「二の表・名殘りの表」には二句から三句を詠まねばならない、本來、この『戀』は源氏物語の『戀』を意味してゐた。
また、發句に月が詠まれた場合は、「初折」の『月の座』は省かれる。
最後に、連歌の發句と、獨立した「發句」の違ひを述べれば、芭蕉の有名な句、
暑き日を海にいれたり最上川
といふ句があるが、これが連歌になると、
涼しさや海に入れたる最上川
と詠まれてゐて、一句の獨立(どくりつ)性が失はれて挨拶の句となつてゐる。
何故、獨立性が缺如(けつじょ)したかといふと、
主題の、「涼しさ」を句中に押込めて獨立した「發句」と、
それを挨拶として前面に表現してしまつた、連歌の發句を考へれば納得するだらう。
これは藝術に於ける文學と、日記や手紙の差であると言へまいか。
參考文獻
岩波講座「連歌及び連歌史」 山田孝雄 岩波書店
連歌の作法 その四、
「その二」で掲載した連歌は、お樂しみ戴けただらうか。
今囘はそれらの句に應(おう)じて、それぞれの句の解釋(かいしやく)と、作法とを述べて行きたいと思ふ。
作法に際しては、
『式目』
といふものがあるが、これは樣々なスポオツで、試合を圓滑(ゑんくわつ)に進める爲(ため)にある規則(ルウル)と同じもので、
『「式」は方式・「目」は條目』
の事で、有名な所では、「貞永式目(御成敗式目)」や「建武式目」がある(大辞林)。
先づ初めの句は、「初折(しよをり・六句)」の中の第一句で、
「初折」の「發句」の「秋」
夕暮の目にせまりくる瀧紅葉 甲子
これを發句(ほつく)と言ひ、發句には、『季語・切字』が必要で、
『季語』
は、客が主人に玄關で挨拶をする感じであり、それは手紙の時候の挨拶と通じる事は、既に述べた通りであるから、時期にあつたものを選ばなければならないと言へるだらう。
さうして、連歌の座では、發句は生來、技術の熟達した者が詠む事になつてゐるが、優秀な師なり「捌(さば)き手」があれば、初心者でもかまはないと言ふ事になつてゐる。
但し、初心者の句は、それらの人の手によつて推敲されるのを常とするので、不服を申し立ててはならない事になつてゐる。
また、「捌き手」も座の雰圍氣(ふんゐき)を壊(こは)さないやうに、細心の注意を拂(はら)はなければならない。
『切字(きれじ)』に就いては筆者の「發句雜記」で述べたいと思ふので、それを參照してもらへれば良いのだが、それでも簡單に言ふと、
『切字』とは、上の言葉と下の言葉をイコオル(=)で結ぶ役目のものであり、もつと言へば、終止感の強調の爲だ、とだけは言つておかう。
これは日本語の膠着語(かうちやくご)といふ特質を利用した、實(まこと)に見事な表現理論だと言へるだらう。
さて、句の意味は、
「夕暮になつて、暗さの爲に周りの景色が見えず、瀧と紅葉(もみぢ)が、まるで眼前に迫るやうに見えた」
といふ意味ではあるが、
「紅葉の色が目に迫る」
のは兔(と)も角(かく)、
「瀧の音さへ耳に聞えるのではなく、目に迫る」
と言つた處が着眼點(ちやくがんてん)である。
一體(いつたい)、發句は、
「品高く、姿よきこと」
を第一とし、
「時・場所・事情」
とが一句中にあるのが理想とされてゐる。
次の脇「第二」の、
「一の折」の「脇」の「秋」で、
途切れし音に秋は去りつつ 乙女
「七七」の脇句は發句を受け、その餘情(よじやう)を盡(つく)して挨拶をかへすのであるから、必ず發句の季に從(したが)ふのが約束である。
本來、附句(つけく)とは前句の説明だけにあるのではなく、戀愛(れんあい)中の男女の關係に似て、男の個性と女としての個性が調和するといふのでなければならず、ただ男の言ひなりになる女性とか、結婚後に女房の尻に敷かれる男とかのやうな歿個性なものになつてはならないので、一句としての獨立(どくりつ)の價値(かち)がなければならず、而(しか)して前の句との調和をも求められるものである。
で、この句の意味はといふと、發句に、
『「目に迫る」とあるのを受け、五官に他のものを見出せるから、そこにつけ入る可きものがあり、「とぎれし音」として聽官(ちやうくわん)を詠み、「秋」が「去」つて行く』
としたのであるが、ここに土地を明(あきら)かにしてゐないのが疵になつてゐる。
そこで、
音もとぎれし秋の山間(やまあひ)
とするのが理に適ふと言へるだらう。
猶(なほ)、脇句を附けるに際しての骨(コツ)は、體言(たいげん)止め、詰り、名詞を利用するのが安全である。
それが如何なる理由によるかといふと、次の「第三」の句の場合への移り方が、
「發句と同じ境地を詠んではならない」
といふ事と通じるもので、
「同じ境地から立出でざる句」
これを、
「輪廻(りんね)」
と言つて嫌ふのであるが、意味もなく嫌ふのではなく、それをすると三十六句の全てが同じ境地の句となつて、連衆(れんじゆう)で「座」を持つた意味がなくなるからである。
次の「第三」は、
「第三」の「雜」で、
瀬を渡り足を拭へば目を閉ぢて 丙内
といふ句で、ここに見られるやうに、
「て止り・らん止り・もなし止り」
を基本として、この言葉の使用は「三句去り」の規定である。
それと「第三」の内容は、
「たけ高く大樣(たいやう)に」
といふ教へがある。
さて、ここでの句意は、
『「瀬を渡」つてみると水の冷たさに驚いて、「目を」瞑(つぶ)りながら「足を拭(ぬぐ)」つた』
といふもので、内容は問題ないが、無季であるの事が殘念である。
無季の句を「雜(ざふ)」の句といふが、
「春・秋」
の季が出れば、三句は同じ季を續けなければならず、必要ならば五句までは良いが、それ以上は許されない事になつてゐる。
從つて、ここは「秋」を詠まねばならず、
ひやひやと瀬渡る足に目を閉ぢて
とするが良いだらう。
因(ちな)みに、芭蕉の「奥の細道」で有名な句、
唐崎の松は花より朧にて
この句が問題になつたのは、第三句の「て止まり」であるにも拘はらず、これを發句とした處にあつたのが、これで解つたものと思はれる。
參考文獻
岩波講座「連歌及び連歌史」 山田孝雄(やまだよしを・1873-1958) 岩波書店
「連句入門(芭蕉の俳諧に即して)」 東 明雅(1915-) 中公新書
連歌の作法 その五
今囘は、初折の「第四」から始める事になるのだが、その前に、連歌は發句を除けば、前の句に附いても後ろの句に附いても、合せて短歌の態(てい)を成(な)してゐなければならない。
例へば、
音もとぎれし秋の山間(やまあひ)
といふ「第二」の脇は、發句と合せて、
夕暮の目にせまりくる瀧紅葉
音もとぎれし秋の山間
といふ短歌になり、また「第三」の句とも併(あは)せて、
音もとぎれし秋の山間
ひやひやと瀬渡る足に目を閉ぢて
と「七七・五七五」なりますが、これは「五七五七七」と語順を入替へて、
ひやひやと瀬渡る足に目を閉ぢて
音もとぎれし秋の山間
このやうに解り易く考へても構はず、而(しかう)して一句としても、それぞれが獨立の氣風がなければならない處(ところ)に、難(むづか)しさと面白さとがある。
以上の事が解つた上で、「第四」の句の説明を始めたいと思ふ。
「初面」の「第四」の「雜(ざふ)」は
啜(すす)る湯呑に澤庵(たくあん)の味(あぢ) 甲子
といふ句で、「第四」は、
「句姿安らかにすらすらとすべきもの」
であり、これを「四句目ぶり」といふが、なかなかに難しく、「體言(名詞)」で止めてあり、句意は前句の、
『「目を閉ぢて」を受けて、御隱居(ごいんきよ)が茶を嗜(たしな)んでゐる姿を聯想(れんさう)させ、利休の「侘茶」かと見せて、「澤庵」を齧(かじ)つてゐる滑稽な「落(オチ)』となつて結ばれる。
次の第五句目は、「平句」の「冬」の「月の座」で、
ひと聲(こゑ)に素振りをくれて寒の月 乙女
この句は第五の『月の座』だから「月」を詠まねばならないが、單に「月」といふと秋の季節の事で、それぞれの季に應(おう)じたものを詠む事を忘れてはならないだらう。
例へば、春ならば「朧月」、夏は「夏の月」といふやうにだが、この句は「寒の月」だから冬の季節になつてゐる。
しからば、前句との關係は何かといふと、
「素振りをくれて」
といふ處に鍵があり、前句の、
「澤庵」
から人名の澤庵和尚を聯想(れんさう)し、當然、宮本武藏が浮び上がつてくるといふ譯である。
これは、
「面影」
といふ附け方で、「故事・古歌・古物語」を露骨に表現せずに匂はせて止める方法を採用してゐるが、
「初折」には、
「神祇(しんぎ)・釋經(しゃくきやう)・戀(こひ)・無情(むじやう)・無常(むじやう)・述懐(ずゆつくわい)・懐舊(くわいきう)」
更には、
「名所・人名」
は避けるべきものであるから、露(あらは)に澤庵和尚と言へない苦しい處がある。
それと、
「月の座・花の座」
は、それ以前に詠むのはかまはないが、以降に詠む事は許されてゐないので、くれぐれも注意が肝要である。
また、
『猿蓑』
の連歌にある凡兆の發句のやうに、
市中は物のにほひや夏の月
と「月」を詠んでしまつた場合は、五句目の「月の座」には「月」を詠まずに、
此筋(このすぢ)は銀も見しらず不自由さよ
と、芭蕉が式目に緩(ゆる)やかに附けてゐるが、古式に則(のつと)つた連歌では、
「五月(さつき)」
といふ言葉による「月」が發句にあるだけで、五句目の「月の座」には「月」を詠む事を避け、代りに、
「有明」
といふ言葉で「月」を匂はせるやうな心得が要求される。
その好例として、「本能寺の變(へん)」で有名な明智光秀(1528-1582)が、事件直前に愛宕山で催した連歌で、
時は今天が下しる五月かな
といふ發句を詠んだのを受けて、五句目の「月の座」で、
かたしく袖は有明のしも
と詠んだ理由も頷(うなづ)けるだらう。
猶(なほ)、
「夏・冬」
は一句で捨てても良く、必要とあれば三句まで許される。
次の六句は、
「折端(をりはし)」
ともいふが、表から裏へ移る句となつてゐるが、「折端」の「雜」で
誰も咎めぬ夢なればこそ 丙内
この句は幸ひ、
「て止まり」
になつてゐないが、ここで「て止まり」の句を詠む事は三句去つてゐないから駄目である。
実(まこと)に連歌の式目は厄介であるが、色々なスポオツの規則(ルウル)も時に應じて改革されてゐるのだから、現代の人にも扱ひ易い今風の規則になつても、しかる可きかも知れない。
句意は、前の句の、
「寒の月」
の出てゐる深夜に不審な男が大聲で、
「素振りを」
してゐたら警察に捕まると考へて、それを、
「咎め」
られないのは、
「夢」
だからだと詠んだのである。
今囘はここまでとするが、前囘にものべたやうに、
「神祇(しんぎ)・釋經(しゃくきやう)・戀(こひ)・無情(むじやう)」
それに加へて、
「無常(むじやう)・述懐(じゆつくわい)・懐舊(くわいきう)」
更には、
「水邊(みづべ)・山類(やまるい)・居所(ゐどころ)・聳物(そびきもの)・降物(ふりもの)」
といふものを知らねば、
「去嫌(さりぎらい)」
の事が理解出來ないので、それを追ひ追ひ述べながら、
「平句」
の解説をして行きたいと思ふ。
參考文獻
岩波講座「連歌及び連歌史」 山田孝雄(やまだよしを・1873-1958) 岩波書店
「連句入門(芭蕉の俳諧に即して)」 東 明雅(1915-) 中公新書
連歌の作法 その六、『初折六句』
さて、前囘まで述べた内容を調べてみますと、丁度「初表」の六句目で解説が終つてゐましたので、最初に提示された句と、添削されたものとを比較するところから始めてみます。
夕暮の目にせまりくる瀧紅葉 甲子
とぎれし音に秋は去りつつ 乙女
瀬を渡り足を拭えば目を閉ぢて 丙内
啜る湯呑に澤庵の味 甲子
ひと聲に素振りをくれて寒の月 乙女
誰も咎めぬ夢なればこそ 丙内
以上が、連載開始の時に提示された「初折」の部分ですが、「式目」から見ますと可笑(をか)しな處(ところ)があつたのは、これまで述べて來た通りですので、次にそれが添削されたものを列擧します。
夕暮の目にせまりくる瀧紅葉 甲子
音もとぎれし秋の山間(やまあひ) 乙女
ひやひやと瀬を渡る足に目を閉ぢて 丙内
啜る湯呑に澤庵の味 甲子
ひと聲に素振りをくれて寒の月 乙女
誰も咎めぬ夢なればこそ 丙内
この添削されたものと、當初の作品とを比較されると、『連歌』の面白さが解るものと思はれます。
凡(およ)そ、『連歌』の樂しみといふものは、協奏曲に於ける「カデンツア」とか、ジヤズの「セツシヨン」のやうなものだと言へば、お解り戴けると思ひますが、どうでせうか。
ところで、發句の、
夕暮の目にせまりくる瀧紅葉 甲子
といふ句には、「切字」がないやうに思はれるかも知れませんが、
『紅葉』
といふ體言が、その役目をしてゐます。
けれども、初めは、
夕暮の目にせまりくる紅葉かな 甲子
と呼んでゐたのですが、これでは箕面の瀧に來た甲斐がないので、『瀧紅葉』としたのです。
しかしながら、「切字」問題を多くは述べません。
その代りに、
暮れ方や目にせまりくる瀧紅葉 甲子
といふやうに、一般的なものに改作しておきます。
從つて、添削された「初裏」の最終の形は、以下の通りとなります。
暮れ方や目にせまりくる瀧紅葉 甲子
音もとぎれし秋の山間(やまあひ) 乙女
ひやひやと瀬を渡る足に目を閉ぢて 丙内
啜る湯呑に澤庵の味 甲子
ひと聲に素振りをくれて寒の月 乙女
誰も咎めぬ夢なればこそ 丙内
お氣づきの事と思はれますが、これは『連歌』の「歌仙」で卷かれたものですから、「表」が六句となつてゐるので、當初に説明したやうに、『世吉・五十韻・百韻』の場合だと、「初表」は八句となります。
ですから、芭蕉の『奧の細道』にある、
『草の戸も住み替わる代ぞひなの家
面八句を庵の柱に懸置』
といふ部分は、意外と重要な意味を含んでゐると考へられ、『面八句』とは、恐らく『百韻連歌』のものと思はれますが、少なくともその「連歌」の全句を知りたいものだと思つてをります。
七、連歌の作法 『初裏』
それでは、愈々『初裏』の解説に入ります。
裏移り
初 裏 冬 振袖を着せたきままに年越して 甲子
春 枯木も花を身にまとひ 乙女
春 春火事にもろ肌を脱ぐめ組かな 丙内
雜 刺青見せて裁き輕やか 甲子
春 春火事にもろ肌を脱ぐめ組かな 丙内
雜 刺青見せて裁き輕やか 甲子
戀の句 雜 俎の鯉を料理の流れ板 乙女
冬 温もり殘す蒲團抱き締め 丙内
雜 月の座 三月越し二階貸したる人いづこ 甲子
雜 名乘り上げれば御曹司とかや 乙女
春 許されてわが世の春を御散財 丙内
春 驕れる人のうれしかるらん 甲子
春 花の座 無斷にても難色もなし花の宴 乙女
雜 小言が來ても聞 けぬ芳一 丙内
それでは、愈々「初裏」の解説に入ります。
振袖を着せたきままに年越して 甲子
この句は初春を詠んだもので「て止り」ですが、三句を去つてゐるのでこれで良く、年頃の娘を持つ貧乏な親の氣持を披露してゐる譯で、
誰も咎めぬ夢なればこそ 丙内
といふ前句である「初表」の最後の句と合せると、中流家庭の親が見た不吉な夢であつたといふ事になります。
それにしても、「誰も咎めぬ夢なればこそ」といふ句を挾んで展開された、異質な世界を表現する面白さが、皆さんにもお解り戴けた事と思ひますが、いかがでせうか。
前囘は『初裏』の第一句で、
振袖を着せたきままに年越して 甲子
といふ句でしたが、次に展開された句は、前句に長者となつた『かぐや姫』の物語を面影として、「振袖」即ち獨身女性といふ部分に光を當(あ)てながら、
枯木も花を身にまとひ 乙女
と詠む事で、『花咲かぢいさん』を導きだしてゐます。
勿論、「振袖」が「身にまと」ふものである所から、「枯木」が何かの拍子に「花」を咲かせた事を、「まと」つたと表現したものですが、これが次の、
春火事にもろ肌を脱ぐめ組かな 丙内
といふ句では、江戸時代の消防署である「纏持(まとひもち)」に變換(へんくわん)されてゐる譯です。
但し、ここで注意をしなければならないのは、下句の「かな」は切字の最たるもので、發句以後は平句ですから、切字があるのは良くありません。
といふ事で、「め組かな」といふ部分を變へなければなりませんが、だからと言つて「纏持」とすると、前の句の「身にまとひ」の「まとひ」と重複するので、
春火事にもろ肌を脱ぐいろは組 丙内
と改めた方が妥當(だたう)でせう。
時代背景としては、前の「お伽噺」の世界から、歌舞伎や浄瑠璃へと移行してゐると言へませうか。
九、連歌の作法
前囘の、
春火事にもろ肌を脱ぐいろは組 丙内
の句を受けて、
刺青見せて裁き輕やか 甲子
と詠んだ句は、講談の面白さを狙つてゐて、「もろ肌を脱ぐ」のは「櫻判官」と世に謳(うた)はれた遠山金四郎(?-1840)の「お白州」が一番だ、と輕く詠んで見せたのです。
けれども、ここで一寸問題があります。
それは「初裏」の二句目、「枯木も花を」の「花」と、この四句目の「櫻を見せて」の「櫻」とで、「花」が二つあり、後の十一句目の、
『花の座』
で花を詠まなければんりませんから、それを含めると三句もの數になつてしまひます。
一體に、『月の座・花の座』は、『月の座・花の座』までに詠めば良くて、それを過ぎてはならない事の目印として『座』が設けてあるのですが、やがてそれが形式化してしまつて、こんにちのやうな窮屈なものとなりました。
それでも「月」や「花」は、各折に一つのものである事に變りがありません。
そこでこれの解決策として、
枯木も華を身にまとひ 乙女
と、『花』を「華」に變化させる事とします。
これでも本來は苦しいのですが、この邉(あた)りが筆者の限界といふ事で次に移ります。
猶、「初裏」の第四句目である、この句の「櫻」に關しては、「櫻」といふ語は『花の座』以外で詠まれた場合は、
『「花の句」としては執扱(とりあつか)はず』
といふ事になつてをります。
勿論、『花の座』で詠まれた「櫻」は、「花」である事に違ひはありませんが……。
さて、それを受けた次の句は、
俎の鯉を料理の流れ板 乙女
奉行である遠山金四郎は人を「裁(さば)く」ところから、それが板前の庖丁「捌(さば)き」へと移行したもので、これは流行歌にもある、
『月の法善寺横丁』
の雰圍氣を醸(かも)し出します。
當然、それを受けた次の句は、
温もり殘す蒲團抱き締め 丙内
「鯉(こひ)」から「戀(こひ)」へと變化させ、田山花袋(1871-1930)の文學作品、
『蒲団』
の世界を垣間見せる譯ですが、
『戀の句』
は十二句目からが良いといふ約束があり、それまでに「戀」を詠むと、
『待ち兼ねる戀』
と言つて嫌はれてゐます。
この句は「初折」から十二句目ですから、文句はありません。
前囘の、
温もり殘す蒲團抱き締め 丙内
といふ「戀の句」を受けて、
三月越し二階貸したる人いづこ 甲子
といふ句になりますが、この句は「初裏」の、
『月の座』
に當りますが、「三月越し」の「三月」が『月の座』として穩當(をんたう)であるかといふと、問題がないとは言へませんので、
冬の月二階貸したる人いづこ 甲子
とでもして措(お)きませう。
意味は、下宿させてあげたものの、家賃を滯納した儘、こんな冬の夜寒を、何處へ行つたものやら、といふ家主の心境と言つた所でせうか。
それを受けて、
名乘り上げれば御曹司とかや 乙女
といふ脇は、行方知れずだつた下宿人が、
「その節は、ご迷惑をお掛け致しました」
と言つて現れた時の驚きで、しかも大會社の社長の息子であつた、といふ二重の驚きが表現されてゐる譯です。
いやはや、人には親切にするものですな。
十一、連歌の作法
前囘の、
名乘り上げれば御曹司とかや 甲子
それを受けてかう詠んだ。
許されて我が世の春を御散財 乙女
ところが折角、勘當(かんだう)が許されたにも拘はらず、親の舌打ちには振向きもせずに、遊びを覺えた分だけ、却つて金遣ひもひどくなつてゐる始末。
矢張、ドラ息子は直つてゐなかつたといふ事で、親はいつでも子供に苦勞させられるものらしい。
次の句は、
驕(おご)れる人のかすむうれしさ 丙内
そこで、いつまでもそんな我儘(わがまま)はゆるされないぞ、と、
『平家物語』
が出現する。
第三者の目は、いつも嚴しい。
前囘の、
驕れる人のかすむうれしさ 甲子
それを受けてかう詠んだ。
無斷にても難色もなし花の宴 乙女
他所(よそ)の敷地に咲く櫻を、斷りもなく花見に興じたが、一年に一度のこんな日には、地主も風流を解して文句を言はないものだ、と決めつけてゐる人のなんと多い事か。
續いて、「観音開き」になるけれども、これも、『平家物語』から、
小言が來ても聞けぬ芳一 丙内
それぢや、もしも文句がきたらどうするのかといふと、前の二句が『平家物語』からの引用だから、『平家物語』といへば琵琶法師を忘れてはならず、琵琶法師と言へば「芳一」で、「芳一」は耳が不自由だから、小言も聞けないといふ事になつてしまひます。
と以上ここまでが「初折の裏」の十二句ですが、十二句の違ひを比較して見ると次のやうになる。
振袖を着せたきままに年越して 甲子
枯木も花を身にまとひ 乙女
春火事にもろ肌を脱ぐめ組かな 丙内
春火事にもろ肌を脱ぐいろは組 丙内
刺青見せて裁き輕やか 甲子
俎の鯉を料理の流れ板 乙女
温もり殘す蒲團抱き締め 丙内
三月越し二階貸したる人いづこ 甲子
冬の月二階貸したる人いづこ 甲子
名乘り上げれば御曹司とかや 乙女
許されてわが世の春を御散財 丙内
驕れる人のかすむうれしさ 甲子
驕れる人のうれしかるらん 甲子
無斷にても難色もなし花の宴 乙女
小言が來ても聞 けぬ芳一 丙内
さうして、形を整へて、
振袖を着せたきままに年越して 甲子
枯木も花を身にまとひ 乙女
春火事にもろ肌を脱ぐいろは組 丙内
刺青見せて裁き輕やか 甲子
俎の鯉を料理の流れ板 乙女
温もり殘す蒲團抱き締め 丙内
冬の月二階貸したる人いづこ 甲子
名乘り上げれば御曹司とかや 乙女
許されてわが世の春を御散財 丙内
驕れる人のうれしかるらん 甲子
無斷にても難色もなし花の宴 乙女
小言が來ても聞 けぬ芳一 丙内
以上が「初折の裏」といふ事になります。
十三、連歌の作法
前囘で「初折の裏」が終りましたので、これで、
「名殘りの表」
に入りますが、ここで少し『連歌』に於いての推敲といふ問題を述べて見ませう。
これまででお解りになつたと思ひますが、『連歌』では「座」もしくは「場」といふものを重要視しますので、個人の主張と全體との調和を考へなければなりません。
從つて「捌(さば)き手」は、それがたとへ他人の作品であつたとしても、全體から見れば不釣合だと思はれる場合は、躊躇なくその作品に手を加へる事になる譯です。
一見、考へますと、これは非常に亂暴(らんぼう)な事のやうに思はれるかも知れませんが、しかし、實(じつ)はこれは個人の作品に於いても重要な事で、いくら個性的だと言つても、獨(ひと)り善(よ)がりな考へだけで、作品を構成する譯には行かないでせう。
そこには讀者にも理解出來るやうな、普遍性がなければならない筈ですから、さう考へれば納得も出來るものと思はれます。
尤も、『連歌』では個人よりも「座(場)」の方を大事にする餘(あま)り、知る限りに於いて、芭蕉などでも他の弟子の作品を、その場にゐる全く違つた弟子の作品として、平氣で提出して濟ましてゐるといふやうな事があつたりしたやうです。
これは何も日本といふ國の特質ではなくて、西洋でもヘンデルやバツハ、モオツアルトの時代では、こんにちのやうに著作權が確立されてゐませんでしたから、歌劇や宗教音樂の中へでも、當時よく流行(はや)つた別の作曲家の音樂を採り入れたりしてゐます。
確かに、『連歌』の場合のやうに人に捌かれたものと、個人の意志で選擇したものとの差はありますが……。
けれども、これはこれで個人の作品を創作する時に、隨分と役立つ事があり、その方がはるかに大切な事で、例へば、『去來抄』に、
『 妻よぶ雉の身を細うする 去來
初は雉のうろたへて鳴、先師曰。去來、かくばかりの事をしらずや。
(略)同じ事を成して、姿とはなる物をとなり。(芭蕉全集・興文社)』
といふ有名な逸話がありまして、これはある句の「脇」に、芭蕉の弟子の去來が、
妻よぶ雉のうろたへて鳴
と詠んだ所、芭蕉は、『句には姿といふものあり』と言ひ、去來はそんな事も知らないのかと言つて、次のやうに推敲しました。
妻よぶ雉の身を細うする
同じ事を詠んでも、「姿」のなんたるかを知らなければならない、と手本を見せたのです。
この事からも解りますやうに、『連歌』は謂(い)はば創作者としての個人を磨く、最も重要な鍛錬の「場(坐)」だつたのだと思はれます。
『連歌』は「座(場)」を以(もつ)て尊しとしてゐますが、この連載では、その「座(場)」で濟ませなければならない事を、讀者にも『推敲の過程』が納得出來るやうに解決をしてゐる譯です。
十四、連歌の作法「名殘りの表(二の折)」
さて、これから「名殘りの表(二の折)」に入りますが、前囘の「初折の裏(一の折)」の十二句目で、
小言が來ても聞けぬ芳一 丙内
と詠んだのを受けて、
行く春の重たき琵琶に腰拔かし 甲子
と詠んだ譯で、「夏・冬」は二句去りで一句から三句まで續き、「春・秋」は五句去りで三句から五句まで續けるのが式目の常道ですが、ここでは一句で捨ててゐて、これは有名な、
行く春や重たき琵琶の抱き心 蕪村
の「本歌(句)取り」で、事の重大さを知つて驚いてゐる樣を表現してゐて、違ひは『切字』の「や」を「の」に變へる事で、平句の態を保つてゐます。
續いて、
明方豆腐を角で買ふなり 乙女
これは失敗した人に對して、
「そんな奴は、豆腐の角に頭をぶつけて死んじまへ」
といふ揶揄とも愛情表現ともとれるもので、決して相手に怒りだけをぶつけたものではないやうに思はれ、愚かな行動を人目を憚つて、明け方に角の豆腐屋でそれを購つたといふのである。
それを受けて「戀の句」で、
召上がれ戀はなま物おはやめに 丙内
と詠んだのだが、「戀の句」は五句まで續けても良く、これは豆腐は「豆が腐る」と書くぐらゐで、腐つたものだからこれ以上は腐りさうもなささうなのだが、豆腐は足が早く、それと同じやうに戀もなま物だから、早くしないと破れてしまふもんだと助言(アドバイス)してゐる樣へと發展させたものである。
十五、連歌の作法
前囘の最後の句、
召上がれ戀はなま物おはやめに 丙内
を受けて、
蝉も螢も老いにうるさし 甲子
と詠んだのだが、これは、
「戀に焦がれて鳴く蝉よりも、鳴かぬ螢が身を焦がす」
を蹈(ふ)まへて、「なま物」だから「おはやめに」といはれても、老いた身には煩(わづら)はしいばかりだと、あるいは「おはやめに」しなかつたばかりに、老いの身となつたしまつた、と返したのである。
それには、
宵宮の祗園(ぎをん)囃(ばやし)に馴染(なじみ)客 乙女
と應(こた)へて、藝者遊びに馴れた旦那衆は、最早「惚れた腫(は)れた」などといふ野暮な事は言はない。
枯れた身には、「蝉の螢も」「祇園囃」さへも「うるさ」く感じられるものだといふ境地か。
さればと、
主が命と送る後朝(きぬぎぬ) 丙内
と詠んだのだが、
『後朝(きぬぎぬ)』
とは一夜を共にした男女が朝の別れを惜しんで、貴方が「命」だと可愛い事をいふのである。
「遊女は客に惚れたと言ひ」
まさに、これである。
鼻を伸ばしてゐると身代が傾く。
「傾城(けいせい)」たる所以(ゆゑん)であらう。
十六、連歌の作法
前囘の最後の句、
主が命と送る後朝(きぬぎぬ) 丙内
と詠んだのだが、それに對(たい)して、
べろを出し惚れた晴れたも藝の内 甲子
「惚れた」と言つた遊女が舌の根も乾かぬ内に、客が歸つた後にケロツとして欠伸(あくび)をするのである。
その昔、惚れた證(あかし)に指を詰めて相手に渡してゐたのだが、いろんな男に渡すのに小指を調達するのが大變だつたとの事で、手練手管を使つて客を次々と捌いて行くのである。
ここまでは「戀の句」で、「式目」では二句以上で五句までとなつてゐるが、それほど細かく氣にする必要はない。
ずんずんと進んで行つて、停滯感がなければそれで良いと鷹揚に構へてゐれば宜しからう。
次は、
口を開けたら閻魔驚く 乙女
といふ句だが、前の句の「べろを出し」を受けて、それほど嘘をつくぐらゐだからべろが二枚あるかと思つたら一枚しかないので、地獄の閻魔も吃驚(びつくり)したといふのである。
そんな風に考へるほど、人間に比べたら閻魔大王も純情なものである。
さればとて、
金次第とは云へ行けるも地獄だけ 丙内
といふ事で、金に飽かして天國へでも行けるのかと思つたら、
「地獄の沙汰も金次第」
といふ譯で、金があつても行けるのは地獄だけだと思ひ知らされるのである。
十七、連歌の作法
前囘の最後の句、
金次第とは云へ行けるも地獄だけ 丙内
これを受けて、
笑ひ飛ばして住めば都か 甲子
こんな所はいやだと思つてゐると住み難(にく)いが、
「郷に入つては郷に從ふ」
で、地獄でさへ「住めば都」だと「笑ひ飛ば」さうといふのである。
これには、
身じろぎて男が月に吠える影 乙女
と詠んで、こんな世界だから「アンダア・ワアルド」の住人らしく、中には「狼男」の影が見え隱れする。
もしかすると、探せば「吸血鬼(バンパイア)」や「木乃伊(ミイラ)男」、「フランケンシユタイン」だつてゐさうなものである。
かやうに變化に富んだ世界へと、滯らずに移行して行く樂しみが『連歌』の醍醐味であるが、「月に吠える」とくれば當然の如く、その次に來るのは、
野の虎でさへ元は詩を詠む 丙内
と中島敦(1909-1942)の、
『山月記』
の登場と相成る譯である。
科擧(くわきよ)に受かつて將來を嘱望された主人公が、人間關係に躓(つまづ)いて左遷され、それに疲れて旅の途次に虎に變身してしまふのである。
人間が虎になれる譯のもぢやないが、彼の滿たされない出世欲が妬(ねた)みや驕(おご)りとなつて、破綻してしまつた人生の心の状態を實體(じつたい)化した表現として、虎として變身した姿で表現されるのである。
これが萩原朔太郎(1886-1942)の、
『月に吠える』
だと犬になつてしまふ。
黒猫も屋根の上で鳴いてはゐるが、同じネコ科だとは云へ虎とは大違ひで、「猫を被る」ぐらゐの器量があれば、社會をうまく渡つて行けただらうに、融通の利かない虎であるところに彼の惱みの深さが窺(うかが)はれて、人に飼はれるのを拒否するやうな野生ゆゑの哀れさがある。
と以上で「二の表(名殘りの表)」が終りとなりました。
十八、連歌の作法
前囘で「二の表(名殘りの表)」が終つて、「二の表(名殘りの表)」までを、以下に示せば、
呼 稱 季 解 説 實 例 作者
初 折 發 句 秋 暮れ方や目にせまりくる瀧紅葉 甲子
一の折 脇 秋 音も途切れし秋の山間(やまあひ) 乙女
第 三 雜 ひやひやと瀬渡る足に目を閉ぢて 丙内
初 面 第 四 雜 啜る湯呑に澤庵の味 甲
平 句 冬 月の座 ひと聲に素振りをくれて寒の月 乙
折 端 以下同 雜 誰も咎めぬ夢なればこそ 丙
裏移り
初 裏 冬 振袖を着せたきままに年越して 甲
春 枯木も華を身にまとひ 乙
春 春火事にもろ肌を脱ぐいろは組 丙
雜 刺青見せて裁き輕やか 甲
春 春火事にもろ肌を脱ぐいろは組 丙
雜 刺青見せて裁き輕やか 甲
戀の句 雜 俎の鯉を料理の流れ板 乙
冬 温もり殘す蒲團抱き締め 丙
雜 月の座 冬の月二階貸したる人いづこ 甲
雜 名乘り上げれば御曹司とかや 乙
春 許されてわが世の春を御散財 丙
春 驕れる人のうれしかるらん 甲
春 花の座 無斷にても難色もなし花の宴 乙
雜 小言が來ても聞けぬ芳一 丙
雜 小言が來ても聞けぬ芳一 丙
折 立
二の折 春 行く春の重たき琵琶に腰拔かし 甲
雜 明方豆腐を角で買ふなり 乙
二の表 戀の句 雜 召上がれ戀はなま物おはやめに 丙
(名殘 戀の句 夏 蝉も螢も老いにうるさし 甲
の表) 戀の句 夏 宵宮の祗園囃に馴染客 乙
戀の句 雜 主が命と送る後朝 丙
雜 べろを出し惚れた晴れたも藝の内 甲
雜 べろを出し惚れた晴れたも藝の内 甲
雜 口を開けたら閻魔驚く 乙
雜 金次第とは云へ行けるも地獄だけ 丙
雜 笑ひ飛ばして住めば都か 甲
秋 月の座 身じろぎて男が月に吠える影 乙
雜 野の虎でさへ元は詩を詠む 丙
以上であるが、この後は「裏移り」となり、次囘からいよいよ最後の「二の裏(名殘りの裏)」となるのでお愉しみに。
連歌の作法 (流行(はや)り廢(すた)り事情とその所要時間に就いて)
連歌といふものは、やつてみれば結構面白いものである。
けれども、こんにち連歌が一般に普及されない理由の一端として、その最も大きなものは民衆の娯樂が、電視臺(テレビ)や遊戯(ゲエム)器、電腦(パソコン)や果ては携帶電話による遊戯(ゲエム)や音樂観賞と多岐にわたり、趣味が擴散(くわくさん)してしまひ、頭腦を使つた智的で生産的な遊戯よりも、見たり聞いたり指を動かして操作するといふ依存型の遊戯が主流となつてしまつたからで、精神的なものよりも體感(たいかん)的な方へと移行した感がある。
その昔、「曲水(きょくすい)の宴(えん)」といふものがあつた。
丁度、「流しそうめん」のやうに上から流れてくる盃に酒を湛(たた)へながら自分の前に來るまでに、和歌を詠んで一首をものにするのである。
それ程に風流でなくても、昔にしたところが、體感的で依存型の「百人一首」を取り合ひながら、そこから發展して智的で生産的な連歌への道が開けてゐたのだが、さういつたものは今では見受けられず、遊戯(ゲエム)で遊ぶだけでなく、遊戯そのものを作つて見ようとする人がゐたとしても、職業として遊戯(ゲエム)の制作會社といふ專門職の道を選擇(せんたく)してしまひ、作つて遊ぶといふ依存と生産が一體になつたもの、例へば「竹トンボ」を作つて遊ぶなどといふ事が、めつきり減つてしまつたやうに思はれ、それは丁度、作曲家が演奏家を兼ねてゐた時代から、作曲家は作曲を、演奏家は演奏をとそれぞれに分業化が進んでしまつたやうに、素人が連歌の座を設けて遊ぶなどといふやうな事は、とんと見られなくなつてしまつた。
更に、連歌を詠む爲には可成(かなり)の素養が必要であるだけではなく、世知辛い世の中で、連歌は一人で詠む、
「獨吟」
でない限り、複数の人が集まつて共同で作品を完成させるものであるから、
「座」
を興行するに當つては、場所も時間も共有しなければならず、それがどれだけの時間をその爲に割(さ)く事が出来るかといふ問題もあり、それも障害(ネツク)となつて廢(すた)れる一助を擔(にな)つたのかも知れない。
事實(じじつ)、それは江戸時代の芭蕉の頃でさへその兆候は見られ、既に述べた事だが、本來連歌は、「上句・五七五」と「下句・七七」を合せて「百句」になるものを、
『百韻連歌』
と云ひ、俳諧といふ滑稽や機智を重んじたものは、
『無心連歌(栗の本)』
それに對して幽玄で優美な純正な連歌を、
『有心連歌(柿の本)』
といふが、それが基本であつた。
その半分の「五十句」のものを、
『五十韻』
さうして、「四十四句」で一卷とするものを、
『世吉連歌(世久連歌)』
また、「三十六句」で一卷とするものを、
『歌仙』
といふ。
芭蕉以降は、
『歌仙』
の形態が多く見られ、それは初めに述べたやうに、時間を短縮しなければ人が集まらなくなつたのが原因であらうかと思はれる。
ものの本によれば、
「百韻一卷を滿尾(完結)するのに、朝から夜更けまでかかつたといふが、それ程ではなくても、朝から日暮れまでの凡そ十時間前後で、一句平均が六分といふ事になる」
らしい。
僅か六分で、
「整ひました(笑)」
と一句をものにするのは、素人にはかなり難しい事であらう。
これを「歌仙」にすると、四時間弱といふ按配(あんばい)で、お茶や酒を飲んだり、無駄話をする時間はあつても、「連歌」の座を一席などといふ奇特な風流人が、さう何人もゐるとは思はれない。
さう云つた事もあつて、明治以降、發句は俳句となり、連歌を嗜(たしな)む人は少數派となつて今日に到つてゐるのである。
「連歌」が人々から離れてしまつた理由はそればかりではなく、一卷を完成させる爲には煩雜な「式目(ルウル)」があつて、それが一層遠ざける理由ともなつてゐるので、ここで少し「式目」に就いて述べて見たい。
といふのも、芭蕉自身も「歌仙」にして會合の時間を短縮させただけでなく、「式目」を大幅に改良する事で、多くの人が參加し易いやうに間口を擴げたのである。
その有様(ありやう)は、心得として形式は身につけてはおくが、それよりも内面的なものの方を重要視するといふ姿勢で連歌に取組んでゐて、それは例へば、
「戀の句は二句以上から五句まで」
と言はれてゐるのを一句で捨ててゐたり、
「月花の座も出るに任せ、咲くに任せて苦しからず」
といふぐらゐだから、松尾芭蕉は「式目(ルウル)」から離れる事によつても、參加者や弟子を増やす事に成功して一時代を築いたのである。
こんにち、「連歌」を多くの人と樂しまうとすれば、三十六句で一卷とする『歌仙』はその儘(まま)としても、「式目」は芭蕉の時代よりも更に緩(ゆる)やかにしなければ、とてもではないが多くの人がついて行けないだらう。
その理由としては、
「宗匠と執筆」
の存在が必要であつた芭蕉の頃のやうに、一卷全體を見渡してそれぞれの句を吟味、添削したり、「式目」に精通した捌き手である進行役が、簡單には周りで調達出來ないからで、ここで最初に示した「全三十六句」、
連歌の作法 その二
のやうな輕い「式目」を根柢(ベエス)にして、みんなが集まつて座の興業が出來ればと願ふばかりである。
參考文獻
岩波講座「連歌及び連歌史」 山田孝雄 岩波書店
連句入門(芭蕉の俳諧に即して) 東 明雅著 中公新書
二十、連歌の作法「二の裏(名殘りの裏)」
さて、いよいよ最後の「二の裏(名殘りの裏)」になつたが、前囘の最後の句、
野の虎でさへ元は詩を詠む 丙内
を受けて、
旅に寝て濡らす枕も袖の中 甲子
と詠む譯だが、「袖を濡らす」とは泣いてゐる事の婉曲(ゑんきよく)的表現で、この世で結ばれる事のかなはぬ人を、旅の夜の獨(ひと)り寢に淋しく偲んで泣いてゐる姿を映したもので、これは「戀の句」と云へるだらう。
續いて、
身に沁む冬の主の情 乙女
と詠んでゐるが、心細い旅の夜空に「情(なさけ)」ある人の親切で、一夜の宿を借りる事が出來た喜びに、「主(あるじ)」の思ひ遣りが「身に沁」み、人の世が捨てたものでもないと、改めて思ひ知つた心境であらう。
ここで、
野の虎でさへ元は詩を詠む 丙内
旅に寝て濡らす枕も袖の中 甲子
身に沁む冬の主の情 乙女
といふ句の、虎から人へといふ變化を愉しんで戴ければ面白からうと思はれるのだが、どうだらう。
ただ次の句の、
因縁の昔語りに夜も更けぬ 丙内
といふ句が、圍爐裏(ゐろり)を前にして一夜語りに、四方山話から身の上話へと移行するのだが、これは前の句に比べて停滯氣味の句境であるといへ、「輪廻」の句になつてゐて、餘(あま)り出來が良くはないが、實力(じつりよく)的にはこれぐらゐのものであらうか。
これで後三句で『連歌の作法』も終りとなる。
以下、次回に譲る事とする。
漸く明けた春はやまぎは 甲子
をかしさに一歩蹈み出す野邊の花 の色 乙女
日に從ひて(し)向日葵(いづこ)の咲く 丙内
二の折 春 行く春の重たき琵琶に腰拔かし 甲
雜 明方豆腐を角で買ふなり 乙
二の表 戀の句 雜 召上がれ戀はなま物おはやめに 丙
(名殘 戀の句 夏 蝉も螢も老いにうるさし 甲
の表) 戀の句 夏 宵宮の祗園囃に馴染客 乙
戀の句 雜 主が命と送る後朝 丙
雜 べろを出し惚れた晴れたも藝の内 甲
雜 口を開けたら閻魔驚く 乙
雜 金次第とは云へ行けるも地獄だけ 丙
雜 金次第とは云へ行けるも地獄だけ 丙
雜 笑ひ飛ばして住めば都か 甲
秋 月の座 身じろぎて男が月に吠える影 乙
雜 野の虎でさへ元は詩を詠む 丙
雜 野の虎でさへ元は詩を詠む 丙
裏移り
二の裏 秋 旅に寝て濡らす枕も袖 の中 甲
(名殘 冬 身に沁む冬の主の情 乙
の裏) 雜 因縁の昔語りに夜も更けぬ 丙
春 漸く明けた春はやまぎは 甲
春 漸く明けた春はやまぎは 甲
春 花の座 をかしさに一歩蹈み出す野邊の花 乙
擧句 春 日に從ひて向日葵の咲く 丙
參考文獻
岩波講座「連歌及び連歌史」 山田孝雄 岩波書店
連句入門(芭蕉の俳諧に即して) 東 明雅著 中公新書
二十一、連歌の作法「二の裏(名殘りの裏)」
さて、「二の裏(名殘りの裏)」の最後三句になつたが、前囘の最後の句、
因縁の昔語りに夜も更けぬ 丙内
といふ句を受けて、
漸く明けた春はやまぎは 甲子
と詠んだが、これは明らかに清少納言の『枕草子』からの引用である。
前句の暗く沈んだ句の調べから一轉(いつてん)して明るい朝日の世界が眼前に廣がつた感がある。
それ對して、
をかしさに一歩蹈み出す野邊の花 乙女
この句は『花の座』にあつて、連歌での花は、櫻が基本であるから、「野辺の花」といふ草花の扱ひよりも、
をかしさに一歩蹈み出す花の色 乙女
とする事で、小野小町の、
花の色は移りにけりないたづらに
わが身世にふるながめせしまに
を面影として、しかし、宴(うたげ)も終りに近いので明るくまとめて見ればどうか。
愈々(いよいよ)、擧句(あげく)となる譯で、
日に從ひて向日葵の咲く 丙内
と詠んだが、「擧句の果」といふ言葉はここから生れてゐて、「鯔(とど)の詰り」と同じ意味の用法で使用される。
句意は、早くも春から來(きた)るべき夏を探して、新たな旅立ちといふところなのだらうが、「咲く」は語り過ぎで、芭蕉の、
「語りおほせてなにかある」
といふひ言葉もあるので。
日に從ひし向日葵いづこ 丙内
と控へ目に詠んで、向日葵の背後の入道雲が讀者の腦裡(なうり)に浮べば成功といふところか。
以上で『連歌の作法』は完結するのだが、筆者の知識不足もあつて、全てを語り切る事が出來なかつた。
けれども、これから連歌の座に參加しようと思ふのならば、難しく考へずに、どんどん作句をすれば良からうと思ふ。
まづ何よりも、慣れるとといふ事が肝要だと思ふからである。
『連歌の作法』
とは言つたが、これを書いてゐて、作法は『花の座・月の座』に重點をおくだけで、あとはそれほど喧(やかま)しく言はなくても構はないと思ひ到つた次第である。
最後に讀者諸氏に寄す。
連歌をして見ません?
二の折 春 行く春の重たき琵琶に腰拔かし 甲
雜 明方豆腐を角で買ふなり 乙
二の表 戀の句 雜 召上がれ戀はなま物おはやめに 丙
(名殘 戀の句 夏 蝉も螢も老いにうるさし 甲
の表) 戀の句 夏 宵宮の祗園囃に馴染客 乙
戀の句 雜 主が命と送る後朝 丙
雜 べろを出し惚れた晴れたも藝の内 甲
雜 口を開けたら閻魔驚く 乙
雜 金次第とは云へ行けるも地獄だけ 丙
雜 笑ひ飛ばして住めば都か 甲
秋 月の座 身じろぎて男が月に吠える影 乙
雜 野の虎でさへ元は詩を詠む 丙
雜 野の虎でさへ元は詩を詠む 丙
裏移り
二の裏 秋 旅に寝て濡らす枕も袖の中 甲
(名殘 冬 身に沁む冬の主の情 乙
の裏) 雜 因縁の昔語りに夜も更けぬ 丙
春 漸く明けた春はやまぎは 甲
春 漸く明けた春はやまぎは 甲
春 花の座 をかしさに一歩蹈み出す花の色 乙
擧句 春 日に從ひて向日葵いづこ 丙
參考文獻
岩波講座「連歌及び連歌史」 山田孝雄 岩波書店
連句入門(芭蕉の俳諧に即して) 東 明雅著 中公新書
二十二、連歌は文學に非ざるか
もうお氣づきかも知れないが、正直に云ふと筆者は「連歌』をそれほど詳しく理解してゐない。
だから説明不足や解説し切れてゐない部分も多々あつたと思はれ、それは例へば『序破急』といふものにも言及できなかつた事は、自身の能力のなさを憾(うら)むばかりである。
それらを補はうと、この『連歌の作法』を連載するに當(あた)つて、文獻として二つの書物を參考にさせてもらつた。
一つは、三十年ほど前に購入した山田孝雄(やまだよしを・1873-1958)氏の、
岩波講座「連歌及び連歌史(岩波書店)」
といふ作品で、これはもう一つの作品よりも先に入手したものであり、これを師匠と仰いで隨分と勉強した心算(つもり)なのだが、何せ相手は生身ではなく書物なので、手取り足取りといふ譯にはいかず、とてもではないが一子相傳などといふやうな奧義を極めるまでには至る事が出來なかつた。
そこでこれを書いてゐる途中に偶々(たまたま)古本屋で手に入れる事が出來た、もう一つの書物が東明雅(1915-?)氏の、
連句入門(芭蕉の俳諧に即して)中公新書
といふ作品を第二資料としたのだつたが、それとても「連歌」の世界は廣がるばかりで、淺學の徒であるわが身を思ひ知らされる結果となつてしまつた。
ただ、この書物の中で氣になつた箇所があつて、しかもそれは「文學とは何か」といふ問題に深く拘はつてくると考へられるので、それについて筆者の考へを開陳して見たいと思ふ。
少し長いがそれを示せば、
『俳諧は(中略)一定の句数でひとまとまりにするものであるが、そのひとまとまりには、一貫したテーマ、あるいは筋というものが存在しない。(中略)各句の中にはいろいろのものが登場してくるけれども、それらが全部、関係しあって、全体で一つの主題、あるいは何か筋めいたものを表現するのではなく、(中略)(獨立した)世界と世界、それらが並んでいるだけである。』
『このような現象も、外国の詩には全くありえない。西洋の詩でも、あるいは中国の漢詩であっても、詩にあってはすべて、第一行は第二行に展開し、第二行は第三行へと発展し、さらに第一聯は第二聯へ、第二聯は第三聯へと、それぞれ内容的に緊密につながり、思想・構成の上にも統一を保ち、全体として作者の主題を有効に表現する。それが彼らの詩なのである。』
『それに比べて、俳諧は作品全体として、一貫した主題がなく、三十六句なら三十六句、百句なら百句、それぞれが一つになり、全体としてはっきりした何かを表そうとして、互いに協力しあい、あるいは響きあうということは、あまりない。この点が、西洋の詩と俳諧の根本的な相違点の一つである。だから、これが俳諧の欠点とされ、いわゆる連俳非文学論の論拠とされたのであつた。』
これに續いて、正岡子規(1867-1902)の作品を掲載してゐる。
『明治二十八年、正岡子規の『芭蕉雑談』の中で、「発句は文学なり、連俳(俳諧)は文学に非ず、……連俳固(もと)より文学の分子を有せざるに非ずといへども文学以外の分子をも併有するなり。面して其の文學の分子のみを論ぜんには発句を以て足れりとなす(中略)。連俳に貴ぶ所は変化なり。変化は即ち文学以外の分子なり。蓋し此変化なる者は終始一貫せる秩序と統一との間に変化する者に非ずして全く前後相串聯(かんれん)せざる急遽倏忽(きふこしゆくこつ)の変化なればなり。例へば歌仙は三十六首の俳諧歌(?筆者註)を並べたると異ならずして唯両首の上半句若しくは下半句を有したるのみ」』
以上の文章で、このいづれもが俳諧には主題(テエマ)がないので、それをして文學とは認められない論據としてゐるのである。
勿論、著者の東明雅氏はこれに反對の立場を主張してをられる。
筆者も同じ立場で、かういふ論理が本當に通用すると思つてゐるのかと云ひたい。
もしさうだとすれば、極めて稚拙な文學論だと言はねばならないだらう。
文學の主題とは、所詮人間が如何に生き、如何に死ぬかといふ事であるから、主題がないとは片腹痛くてお話にならない。
人間の生活の一部を切取つた風景でも、自然の觀察であつたとしても、人間のみならず人間の目を通した自然を書くといふだけで、充分に文學足り得るのである。
さうでなければ、國木田獨歩(1871-1908)の『武蔵野』は文學とは云へない事になつてしまふではないか。
一體(いつたい)、文學とは我が國では物語とか隨筆や日記文學などがあつて、
物語は『源氏物語』や『竹取物語』とか『今昔物語』あるいは『平家物語』などがあり、物を語るといふぐらゐであるから、事件を追ひかけるといふ筋立てがあるので洋の東西を問はず、主題がある文學といへるだらう。
ところが隨筆は、『枕草子』や『方丈記』が代表として掲げられ、生活の身邊雑記を述べる形式のもので、主題とは遠い文學形式であるといへるのは御存じの通りである。
また日記は『蜻蛉日記』や『土佐日記』などがすぐに思ひつくが、しかし、『土佐日記』などは『蜻蛉日記』や『紫式部日記』などに比べると、日記といふ題名ではあるものの、どちらかと言へば紀行文學と云つた方が良くて、『更級日記』とか『十六夜日記』も『奥の細道』のやうな紀行を中心とした種類(ヂヤンル)であると思はれる。
さういふ意味では随筆や日記や紀行文學は、十八世紀以降に確立された小説のやうな主題を提示する文學形態とは異なつて、漫然と、と云つて都合が惡ければ、漠然(?)と人生の善し惡しを書き綴つてゐる譯だが、それでも日常の朝食の獻立(こんだて)だけだとか、天候や仕事の愚痴だけを書いたものではなく、そこはそれ、作家の業といふか、本當に個人だけが解ればいいといふ日記として書いたものではなく、人樣に見てもらはうといふ表現方法が驅使されてゐて、主題はなくとも普遍的な内容に仕立てられて發表されてゐる。
主題といふものが、例へば「友情」とは何かと大上段に振りかぶつた命題を掲げた文学作品だけが、さうだといふのであれば、狭義に過ぎるのではないか。
芥川龍之介(1892-1927)が谷崎潤一郎との文學論争で唱へた『筋のない小説』といふ程でないにしても、判り易い明確な主題が見つけられなくても、文學を樂しみ味はふ事は出來る筈である。
何故ならすべての文學作品には、人生とはなんぞやといふ最大の主題(テエマ)が横たはつてゐるのだから……。
二〇一〇年十月七日午前二時四十分
岩波講座「連歌及び連歌史」 山田孝雄 岩波書店
連句入門(芭蕉の俳諧に即して) 東 明雅著 中公新書
二十三、完成された連歌
これで『連句の作法』における解説は終つた事になる。
敢(あへ)て「近江派」と呼ぶ程のものではないが、最後に、『歌仙』の全句を掲載する。
呼 稱 季 解 説 實 例 作者
初 折 發 句 秋 暮れ方や目にせまりくる瀧紅葉 甲子
一の折 脇 秋 音も途切れし秋の山間(やまあひ) 乙女
第 三 雜 ひやひやと瀬渡る足に目を閉ぢて 丙内
初 面 第 四 雜 啜る湯呑に澤庵の味 甲
平 句 冬 月の座 ひと聲に素振りをくれて寒の月 乙
折 端 以下同 雜 誰も咎めぬ夢なればこそ 丙
裏移り
初 裏 冬 振袖を着せたきままに年越して 甲
春 枯木も華を身にまとひ 乙
春 春火事にもろ肌を脱ぐいろは組 丙
雜 刺青見せて裁き輕やか 甲
春 春火事にもろ肌を脱ぐいろは組 丙
雜 刺青見せて裁き輕やか 甲
戀の句 雜 俎の鯉を料理の流れ板 乙
冬 温もり殘す蒲團抱き締め 丙
雜 月の座 冬の月二階貸したる人いづこ 甲
雜 名乘り上げれば御曹司とかや 乙
春 許されてわが世の春を御散財 丙
春 驕れる人のうれしかるらん 甲
春 花の座 無斷にても難色もなし花の宴 乙
雜 小言が來ても聞けぬ芳一 丙
雜 小言が來ても聞けぬ芳一 丙
折 立
二の折 春 行く春の重たき琵琶に腰拔かし 甲
雜 明方豆腐を角で買ふなり 乙
雜 明方豆腐を角で買ふなり 乙
二の表 戀の句 雜 召上がれ戀はなま物おはやめに 丙
(名殘 戀の句 夏 蝉も螢も老いにうるさし 甲
の表) 戀の句 夏 宵宮の祗園囃に馴染客 乙
戀の句 雜 主が命と送る後朝 丙
雜 べろを出し惚れた晴れたも藝の内 甲
雜 口を開けたら閻魔驚く 乙
雜 金次第とは云へ行けるも地獄だけ 丙
雜 笑ひ飛ばして住めば都か 甲
秋 月の座 身じろぎて男が月に吠える影 乙
雜 野の虎でさへ元は詩を詠む 丙
雜 野の虎でさへ元は詩を詠む 丙
裏移り
二の裏 秋 旅に寝て濡らす枕も袖の中 甲
(名殘 冬 身に沁む冬の主の情 乙
の裏) 雜 因縁の昔語りに夜も更けぬ 丙
春 漸く明けた春はやまぎは 甲
春 漸く明けた春はやまぎは 甲
春 花の座 をかしさに一歩蹈み出す花の色 乙
擧句 春 日に從ひし向日葵いづこ 丙
以上が「歌仙一卷」といふ譯である。
出來の善し惡しは讀者の判斷に任せるとして、筆者は『發句雑記』の方へと分野(フイイルド)を移す事にする。
それに發句集「莫差特(モオツアルト)」も未完の儘である。
やり殘した事はあまりに多くて、過去の作品ばかりを發表してゐる場合ではないのだが、だからと言つてそれまでの作品をその儘にしてもおけず、なんて愚痴をこぼしても仕方がないか。
ともかくも、「箕面吟行」の中の連歌を教本(テキスト)とした『連歌の作法』は、これで完結した事になつた譯である。
これまでの讀者諸氏のおつきあひに感謝の意を述べて筆を擱く事にする。
二〇一〇年十月二十五日午前二時過ぎ
二十四、後記 (連歌といふ特性)
藝術は一般的には個人によつて創作されるものであると普通には思はれてゐて、複數の人達によつて製作される「連歌」などは古今東西を通じても極めて稀(まれ)で、特異な文學形態であると考へられてゐるが、それは「短詩形」で完成された形式が、日本獨自のもので、他國では餘(あま)り見かけられない事も理由の一つとして掲げられるだらう。
「短詩形」とは、短い文章であつても中途半端な言葉足らずのものではなく、それだけで完結性のある文章でなければならず、「發句」はまさにそれを具備した究極の「短詩形」で、その秘密は「季語」と「切字」の中にあると言へるだらう。
抑々(そもそも)、個人によつて完成された作品は固(もと)より個人の著者と考へられるのに何の不思議もないが、それでは「連歌」などの複數の作者によつて完成された作品は、誰を著者とすればいいのか。
さう言つた事に對(たい)する答へは用意されてゐない譯ではないが、多くの人には理解し難(にく)く、特に西洋の文學者達には僅かに小説などに例があるかもしれないが、詩となると全くの不案内で途惑つてしまふのだらう。
一時、西洋の詩人が集まつて「連歌」を詠む試みが催されたと東明雅氏の著者、
「連句入門(芭蕉の俳諧に即して)中公新書」
の中に紹介されてゐるが、それは、
『一九六九年(昭和四十四年)四月、この実験が行われ、ヨーロッパで有名な四人の詩人がパリに集まって、連歌を作った。この作品はあとでガリマール社から出版された』
との事で、この「連歌」に對する感想を、連衆の一人の詩人オクタビオ・パスの言葉を引用して、
『西洋の信仰と撞着する思想の実践であるが故に、連歌はわれわれにとって、試練であり、小さな煉獄であった。(中略)恥の感覚、私は、他の人たちの前で書き、かれらは、私の前で書く。何か喫茶店で真裸になったり、外人の前で排便をしたり、泣いたりするような感じ。日本人は公衆の前で裸で入浴すると同じ理で、同じ流儀で、連歌というものを作ったのだ。われわれ西洋人にとっては、浴場も、われわれの物を書く部屋も全くの密室で、われわれは一人で入り、恥ずべきことも、名誉あることもかわるがわるやってのける』
と言ひ、更にオクタビオ・パス氏は、何故「連歌」の眞似ごとをしたのかといふ理由を、
『私は連歌の中に二種類の親和を見分けることができる。一つは連歌を支配する論理的考察から、芸術的創造の体験に至るまで、現代詩の中心課題と符合している結合的要素であり、他の一つは連歌という遊戯の集団芸術的性格が作者中心観の危機と、集団詩への渇仰に答えている』
と述べてゐるが、これに東明雅氏は、
『西洋の現代詩人からは銭湯にたとえられる連歌・俳諧であるが、誰でもひとさえ集まれば連歌・俳諧の作品が生まれるわけでは決してない』
このやうに本質を捉(とら)へた意見を述べてをられる。
その上、
『俳諧の一座に最も近いものは、演劇の世界に見出されるのではなかろうか。旅の一座などというが、彼らは何人かが共同して一日の興業を完成しなければならない。そのためには、彼らの間に「志の通ずる」、打てば響く精神共同体的なものが必要である。それが存在しない限り、その芝居は真似事に終るだろう。ただし、彼らは各人、あらかじめ台本が渡されていて、書かれた通りに台詞を言い、ト書きの通りに動けば、それである程度の役目は果たすことができる。ところが俳諧の場合は、一巻の進行を保証する台本は別に用意されていない。ぶっつけ本番で各人がその台辞を自分で考え作りながら進行させていく。しかも、その台辞は一人で心のままに書くのではなくて、他人と共同しながら、他人の台辞を考慮しながら作っていかねばならない。そして、他人の台辞を理解するにも、新しい自分の台辞を考えるにも、極めてわずかの時間しか与えられていない。そうなると、以心伝心というか、時には禅機に近いひらめきで続ける必要がある。それを可能にするのが連衆心である』
といふ鋭い考察を披歴されてゐる。
しかし、飜(ひるがへ)つて考へて見れば、西洋にだつて演劇はある譯であつて、詩と云ふ文學の世界ではないかも知れないが、これによく似た構造を持つた部門(ヂヤンル)があると思はれるのである。
それは、レオナルドダビンチ(1452-1519)やミケランジエロ(1475-1564)のやうな藝術家が「工房」といふ集團(グルウプ)に所屬して、複數の職人が大伽藍の壁畫や彫像などの作品を共同で制作した事と、その本質は變ることがないと考へてゐる。
超現實主義(シユウルレアリスム)の畫家、サルバドオル・ダリ(1904-1989)も自身の大作を一人で完成させれば何箇月もかかる所を、職人に配色を指圖(さしづ)して仕上げたりしてゐるぐらゐである。
この外にも既に述べた、所謂(いはゆる)、文學・美術・音樂を統合した總合藝術と稱される演劇や歌劇・舞蹈劇(バレエ)などがこれに當(あた)り、それが時代を經(へ)て、歌劇から呼名を變へたミユウジカルや、あるいは映畫などへ發展して行つて、こんにちでは漫畫(コミツク)や動畫(アニメ)もさうで、それぞれの作家が制作會社(プロダクシヨン)を興して創作に專念するまでになつてゐる。
さうして、それらの作者は代表者の作品として捉へられ、演劇ならば美術監督や演出家、更に出演者や樣々な小道具係(スタツフ)がゐるものの、劇作家の作品として受取られ、それに音樂が加はつた舞蹈劇や歌劇・ミユウジカルならば、脚本や美術監督の名前は提示されるものの、基本的には作曲者にその名誉が與へられる。
漫畫や動畫にしても、背景を描いたり仕上げをする助手(スタツフ)がゐても、多くは制作會社の代表者が作者を名乘るものと思はれる。
その關係は映畫に於(お)いても同じで、作曲者や美術、更に制作に携(たづさ)はつた全ての人々の上に、映畫監督の名前が冠されるのである。
それに從へば、「連歌」の作者は連座を捌(さば)いた宗匠に、その任を與へるべきだらう。
それは丁度、
『オーケストラに指揮者が必要であるように』
と東明雅氏が本書で述べられたやうに……。
變つたところでは、二人の人間が一人のふりをして筆名(ペンネエム)で作品を發表すると云ふ場合もあるが、これは米國の探偵小説家が有名で、日本では漫畫の世界で藤子不二雄氏がゐるが、かういふ形態は極めて珍しい現象と言へるだらう。
最後に、筆者が映畫表現の素晴らしさに私淑してゐる、黒澤明監督に、
『あかひげ』
といふ作品があるが、これを詳細に分析して見ると、彼は俳句(本當は發句と云ひたいが)の能力が高いのではないかと思はせ、若しかすると「連歌」さへ心得てゐたのではないかと考へられる程の効果が到るところに見受けられる。
奇しくも芭蕉が述べた、
「取合せ」
といふ呼吸のやうなものが、程良く制禦(コントロオル)された形で隨處(ずいしよ)に散見出來る。
いづれ紹介出來れば、稿を改めて發表して見たいと思ふ。
二〇一〇年神無月二十六日(火)午前二時四十五分
參考文獻
連句入門(芭蕉の俳諧に即して) 東 明雅著 中公新書